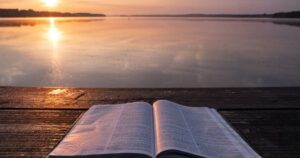黙示録4:4
また、御座の周りには二十四の座があった。これらの座には、白い衣をまとい、頭に金の冠を被った二十四人の長老たちが座っていた。
御座の周りには二十四の座があります
前回は、黙示録4章1節~3節までを学びました。
今、使徒ヨハネは「天」にいます。
それは「この後、必ず起こること」を見るためです。
主は「この後、必ず起こること」を示される前に、ヨハネに「御座」をお見せになりました。
私たちは、決して忘れてはなりません。
「天に一つの御座がある」ということを。
その御座は堅く据えられていて、決して揺れ動くことがないということを。
そして、その御座に着いておられる方が「すべてを治めておられる」のだということを。
このことを心に刻みつけましょう。
私たちは、黙示録の啓示が「御座」から始まるのだということを覚えておかねばなりません。
しっかりと心に留めて、続けて学んでいきましょう。
さて、今回は「御座の周りの光景」について学びます。
これは、どういう位置関係なのかなと思います。
「御座の周り」ということは、御座を中心としてグルっと円形状に「二十四の座」が置かれていたということでしょうか。
この「二十四人の人」は何者なのかと言うことについては様々な意見があります。
- イスラエルの12部族の族長と主イエスの12使徒たち
- 旧約・新約時代の信仰者の代表
- 教会を代表する人々
- 教会の御使いたち
- 地上の患難を通って来た人々
その他にも多くの解釈があるようです。
この24人がどのような人々であるのかは分かりません。
この聖句からはっきりと分かることは、彼らは「長老たちである」と言うことです。
この「二十四人の長老たち」には「座」がありました。
彼らは「御座の前」に座っているのです。
私たちは、キリストにあって「背きの罪の中から生かされ」ました。私たちは「恵みのゆえに」救われました。
私たちの「いのち」は、キリストとともに「神のうちに隠されて」います。
私たちは「ともに天上に座らせ」られているのです。
このように考えると「二十四人の長老たち」は、私たち「贖われた者の代表」と言えるかもしれません。
彼らは「白い衣」を身に着けています。
ヨハネは、この後「白い衣を身にまとう大群衆」を見ます。それは7章で詳しく見ます。
その大群衆が身にまとっている「白い衣」は、子羊の血で白くしたものだと言われています。
長老たちの「白い衣」も、恐らく「キリストを信じる者に与えられる義の衣」であろうと思います。
そして、さらに長老たちは「頭に金の冠」をかぶっていると記されています。
この冠は、主イエスがかぶられる「王冠」ではありません。
再臨の主イエスの頭には「多くの王冠」があります。
原語は「ディアデーマ(διάδημα)」で「主権者の冠」を意味します。つまり「王冠」ですね。原語では複数形になっていますから「多くの王冠」となります。
一方、二十四人の長老の冠は「ステファノス(στέφανος)」で「勝利者の冠(リース)」を意味します。競技者に贈られる「花冠(リース)」のようなものです。
地上の花冠(リース)は、必ず枯れます。しかし、金で編まれたリースは決して朽ちることはありません。
パウロは「走るべき道のり」を走りぬいたと言っています。
パウロの信仰のレースは、終りに近づいていました。
あとは「義の栄冠」を待ち望むだけなのです。
このパウロが待ち望んでいる「義の栄冠」は、原語では「義のステファノス」です。
それは、信仰の戦いを勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終えた人に授けられます。
「主の現われを慕い求めている人」にならば「だれにでも」授けられるのです。
ヤコブは「いのちの冠」について語っています。
「いのちの冠」も同じように「リース」のことを表しています。
私たちに授けられる冠が二種類あるのか、それとも「義の冠」と「いのちの冠」は同じものを現わしているのか、はたまた、もっと何種類もの冠が用意されているのか、それは分かりません。
しかし、この二つの冠(義といのち)の記述から推測するならば、冠を受ける条件は「耐え忍ぶこと」にあるのだと思えます。
私たちは、今、信仰のレースに参加しています。様々な妨害を経験します。楽しみや喜びも伴いますが、苦しみも味わいます。
しかし、決して途中で降りてはなりません。途中で走るのをやめてはならないのです。
冠を受けるまで走り続けましょう。耐え抜いた人には「冠」が与えられます。それは「約束」です。
主は、走り終えた先に「冠」を用意して待っておられます。
私は、この二十四人の長老も「走りぬいた人々」なのだろうと思っています。彼らの頭にある「金の冠」は、試練で試された信仰の輝きなのかもしれません。
この「二十四人の長老」は「証人」なのではないかと私は思います。
これから起こる「さばき」の証人であり、御子イエスの婚姻の証人でもあるのではないかと考えます。
ボアズは「長老たちを証人として」エリメレクのものを買い取りました。
長老たちは「ボアズとルツの婚姻の証人」です。
「二十四人の長老たち」も、これから起こる裁きのあとに行われる「子羊の婚宴」の証人なのかもしれないなと思います。
彼らは「この後、必ず起こること」のすべてを見ます。そして、その先の祝福をも見届けるのでしょう。
もちろん、それは本当かどうかわかりません。
ただ確かなことは、天には「多くの証人」がいると言うことです。
私たちは「あきらめずに」走り続けましょう。「走るべき道のり」を走り終えたならば、必ず、主イエスが迎えてくださいます。そして、あなたの頭の上には「義の冠」が光輝くのです。
御座からは稲妻と雷鳴がとどろきます
私たちにとって「神の御座」は、主イエスにあって「恵みの御座」です。
私たちは「大祭司キリスト」によって「大胆に恵みの御座に近づく」ことが許されています。
しかし「神の御座」はまた「裁きの御座」でもあります。
「神の御座」からは「稲妻と雷鳴」がとどろいているのです。
これは、シナイ山での出来事を思わせます。
主は、エジプトを出たイスラエルに会うために「シナイ山」に降りて来て下さいました。
主が降りて来られた時、イスラエルはあまりの恐ろしさに震えあがりました。遠く離れて立ち、近づくことができませんでした。
モーセは民に言います。
「神が来られた」のは、民が「神を恐れるため」です。そして、それは「民が罪に陥らないよう」にするためです。
私たちの神は「愛の神」です。恐怖で人を押さえつけるようなことはされません。私たちが近づくのは「恵みの御座」です。私たちは「大胆に恵みの御座に近づく」ことができます。
しかし、決して「神への恐れ」を忘れてはなりません。
私たちは「感謝しつつ、敬虔と恐れをもって」礼拝をささげましょう。
私たちは「神は愛です」というメッセージに慣れてしまって「神はさばき主」であるということを見落としがちです。
使徒の働きを読むと、不思議なことに気がつきます。パウロは書簡では「神の恵み」「神の愛」を強調しているように思いますが、宣教の時には「神のさばき」を強調しているように感じます。
パウロは、アテネで宣教した際、主イエスを「さばき主」として紹介しています。
神が「日を定めて」世界をさばこうとしていると教えたのです。
そして、主イエスの復活こそ「その確証だ」と言ったのです。
アテネの人たちは、パウロを「あざ笑い」ました。
「また、いつか聞くよ」と相手にしない人もいました。
そうです。これが「普通の人」の反応でしょう。
私たちの多くは、このような反応を予測しているので、あえて「さばき」や「復活」などから話さないようにしているのではないでしょうか。
耳障りの良いことばから語って、ゆっくりと心を開いて「寄り添って」伝道しようと試みます。
しかし、私は大いに反省しています。
黙示録を学ぶならば、私たちは「さばき」が迫っていることを確信せざるを得ません。
「神の怒り」が注がれる日は近いでしょう。
誰かに「寄り添う」ことは大切なことです。
しかし「神のみこころ」に「寄り添う」ことは、それ以上に大切です。
主は「怒って」おられます。そして「心を痛めて」おられます。人々が「罪に捕らわれたまま」でいることを望んではおられないのです。
愛する兄弟姉妹。
私たちは「福音」を宣べ伝えましょう。
主イエスの十字架と復活を宣べ伝えましょう。
御父が「ひとり子を惜しむことなく死に渡された」ことを宣べ伝えましょう。
「あなたは愛されています」と叫びましょう。
しかし、同時に「この世界は必ず裁かれる」ということを伝えなければなりません。
「信じたら救われる」と伝えるだけでなく「信じなければ滅びる」ことも伝えなければなりません。
これが「真理」なのです。
そして、主は「すべての人が救われて、真理を知るようになること」を望んでおられます。
今は、私たちには「ヨナの油注ぎ」が必要だと切に感じます。
主はヨナに告げられました。
ヨナは、最初は逃げましたが、主の言われたとおり「宣言」をしました。
そうすると、邪悪で有名な都ニネベは悔い改めたのです。
ヨナは奇跡を行ったわけではありません。癒やしも行いませんでした。
ただ「宣言」しただけなのです。
私は「奇跡」も「癒し」も信じます。主の大いなる御業が行われることを期待しています。
けれど、それにもまして「ヨナの油注ぎ」を求めたいのです。
主はヨナに「宣言せよ」と言われたのです。
ですから私たちも、主のことばを「宣言」しましょう。
「ヨナの油注ぎ」を求めましょう。
その「宣言」によって、主の御力が解き放たれることを切に切に求めましょう。
「ヨナ」について語りたいことが溢れていますが、かなり脱線したので黙示録に戻ります。
四つの生き物について
さて、御座の前の光景をもう少し見てみましょう。
御座の前では「七つのともしび」が燃えていました。これは「神の七つの御霊である」と言われていますから「聖霊様」のことであると考えてよいと思います。
御座の前は「キラキラと輝いていた」ようです。
それは「水晶」のように輝く「ガラスの海のように見える」光景でした。
つまり、どこまでも広く輝いていたということでしょうか。
幕屋は「天にあるものの写しと影」です。
主は、幕屋によって「天にあるもの」を私たちに啓示してくださいました。
モーセは「神の設計図」のとおりに幕屋を建設しました。ですから、私たちは「幕屋」を学ぶことによって「天にあるもの」を知ることができるのです。
そして、今、私たちは黙示録によって「写しと影」の「実体」をほんの少し垣間見ているようです。
しかし、残念ながら時間がありません。「幕屋」との関係については、そのうち「幕屋の学び」をする予定ですので、その時にこの箇所にも触れたいと思います。また「神の七つの御霊」については、黙示録五章で学びます。
今回は「四つの生き物」に注目してみましょう、
これは、何とも不可思議な生き物です。
使徒ヨハネは、この「生き物」の「姿形」について述べています。
はてさて、さっぱり分かりませんね。
ヨハネも「生き物」としか表現ができなかったのでしょう。
「人」なのか「御使い」なのか…
ただそれは確実に「生きているもの」であったと言うことです。四つの生き物は、自由に動いており、言葉を発していました。そこには「いのち」がありました。
ある人は、この生き物を「ケルビムだ」と言います。
また別の人は、この生き物は「セラフィムだ」と言います。
しかし、それはどちらとも断定はできません。「ケルビム」のようにも「セラフィム」のようにも思えます。
強いて言えば「セラフィム」に近いのかなと思います。
エゼキエルは「ケルビム」を見ました。(エゼキエル1章と10章を参考に)
イザヤは「セラフィム」を見ています。(イザヤ6章を参考に)
比べてみると面白いでしょう。興味があれば比較してみてください。
「四つの生き物」の「それぞれの姿」が何を表しているのかについても、諸説あります。
ある人は「御使いの代表だ」と言います。彼らは永遠に賛美しているからです。
「この世の政府」を表していると言う人もいます。ダニエル書に出て来る「獣」は「世界帝国を表わしていた」というのが根拠です。
また、ある人は「生き物の代表だ」と言います。獅子は「動物の代表」、雄牛は「家畜の代表」、鷲は「鳥の代表」、そして「人の顔」はもちろん「人類」を表しています。すべての「被造物」が主なる神を讃美していることを表していると言う解釈です。これは、心躍る解釈ですね。
「天地創造をあらわしている」という人もいます。主が「生き物」を造られたことが示されているという解釈です。「創造主なる神」「すべての主」が啓示されているということになります。
最も多い意見は「これは四福音書に現わされたイエス様の姿だ」と言うものです。
マタイの福音書の主題は「王であるイエス・キリスト」です。「ユダの獅子」である「支配者」としてのイエス様が描かれているのです。「獅子」とは、王であるイエス様の一面を表しています。
マルコの福音書の主題は「しもべであるイエス・キリスト」です。マルコの福音書には「系図」は記されていません。「しもべ」に系図は必要ないからです。「雄牛」は、しもべとして仕えてくださったイエス様の一面を表します。
ルカの福音書の主題は「人としてのイエス・キリスト」です。ですから「系図」は「アダム」までさかのぼります。イエス様は、完全な「神」であり、完全に「人」として生きられました。
ヨハネの福音書は「神であるイエス・キリスト」です。「はじめ」からおられたイエス様を描いています。そして「鷲」は「神性」を象徴すると言われます。
個人的には、福音書に対応しているかはさておき、主イエスのご性質のあらわれではないかなと思っています。天は、いたるところに「イエス様をあらわすもの」があるのではないかと私は思っているからです。
しかし、どの意見も断定はできませんね。
四つの生き物については、ししは獣の代表、雄牛は家畜の代表、人間は被造物の代表、わしは鳥類の代表、とされています。それぞれが神を讃美している様子は、被造物全体が神を讃美していることを表しています。またある人はこれを御使いの代表ではと考えます。またある人は四福音書を表している、という人もいます。黙示録は深いのです。ですから、他の主張を軽視しないで、聖書を文字通り信じて、真理を追究している人たちの考えを重んじて真理を求めましょう。
世の終わりが来る 奧山 実著 マルコーシュ・パブリケーション
天で光景を「あれかこれか」と思い巡らせることも、黙示録の醍醐味であると私は思います。御国に行くまで大いに思い巡らせましょう。それは、地上にいる間だけの「楽しみ」なのですから。
さて「四つの生き物」が「何者か」を知ることより、もっと大切なことがあります。
それは、彼らが「何をしているのか」と言うことです。
彼らは「昼も夜も休みなく」礼拝をささげているのです。
「聖なる、聖なる、聖なる、主なる神、全能者」という声は、今も「天において鳴り響いて」います。
見えない領域において「主の栄光は全地に満つ」のです。
次回は、この続きを学びましょう。天での礼拝について学びます。「四つの生き物の礼拝」と「二十四人の長老たちの礼拝」についてです。
祝福を祈ります。