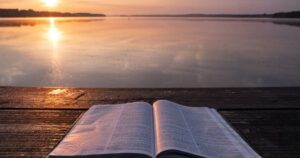黙示録2:4
けれども、あなたには責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。
「けれども」と主は言われます
前回は、黙示録2章1節~3節を学びました。
エペソの教会が「素晴らしく立派な教会」であったことを私たちは知りました。特に「使徒と自称する者たち」の偽りを見抜いたことは称賛に価すると思います。私たちも見習う必要があります。
しかし、そのようなエペソの教会に対して、主イエスは「けれども」と言われるのです。
「けれども、あなたには責めるべきことがある」とイエス様は言われます。
「責めるべきこと」とは、直訳すると「わたしは、あなたに反対している」です。
エペソの教会は精一杯に戦っていました。良い立派な行いをしていました。主の御名のために耐え忍んでいました。どこにも非難するべき点が見つけられない教会です。
しかし、イエス様は「責めるべきこと」があると言われます。エペソの教会とは「反対の立場を取っている」と言われるのです。
その理由は、エペソの教会が「初めの愛から離れてしまった」からです。
すべてのことにおいて正しく、優秀で、立派であったとしても「ひとつのこと」がなければ、イエス様と「反対側」にいると宣告されてしまうのです。
初めの愛とは何でしょう
「初めの愛」とは何でしょう。
まず「初めの愛」とは「落ちることができるもの」であるということです。
エペソの教会は、ある時点までは「落ちて」いませんでした。最初から「落ちて」いたなら、わざわざ「初めの愛から落ちた」とは言われなかったでしょう。
彼らも「初めの愛」の中にかつてはいたのです。
「初めの愛」とは「思い起こすことのできるもの」です。つまり、それは「体験したこと」「経験したこと」であるということです。
エペソの教会は「初めの愛」を知っているのです。知らないものを「思い起こす」ことは不可能だからです。
また「初めの愛」とは、それがなければ「燭台を取り除かれる」ぐらい大切なものです。エペソの教会は「初めの愛」を思い起こし、悔い改め、落ちたところから戻らなければなりませんでした。そうでなければ「燭台」を取り除かれてしまうのです。
「初めの愛から落ち続ける」ならば、教会は、もはや「世の光」ではなくなります。教会としての役割をはたすことはできなくなるのです。厳しく言い換えれば、初めの愛を失うならば「教会ではなくなる」ということです。
つまり「初めの愛」とは「教会のいのち」と言えるでしょう。
それでは「教会のいのち」である「初めの愛」とは、何でしょう?
もう一度、読みます。
「初めに」とは「上等な」「一番大切な」「第一の」とも訳せます。
父親は、放蕩息子に「一番良い衣」を着せなさいと命じています。この「一番良い」と訳されている語と黙示録2:4の「初めの」は全く同じ語が使われています。
エペソの教会は「一番上等の愛」「最も良い愛」から落ちたのです。
イエス様は言われました。
七つの教会には、それぞれに対して「約束」が与えられています。それぞれの教会に即した「約束」が与えられているのです。
エペソの教会には「いのちの木から食べることを許す」という約束が与えられました。
つまり、言い換えれば「このままの状態を続けるならば食べることはできない」ということです。
「初めの愛」から落ちたならば、そして、落ち続けているならば、私たちも「神のパラダイスにあるいのちの木」から食べることは許されないのです。
エデンの園から追放された人は「交わり」を失いました
「いのちの木」は、もともとは「エデンの園」に生えていました。
アダムもエバも「いのちの木」から取って食べて良かったのです。
しかし、彼らは罪を犯しました。サタンに騙され、主に背きました。彼らは「主のことば」よりも「蛇のことば」を選びました。彼らは「食べてはならないと命じられた木から」取って食べました。
そして、どうなったのでしょう?
創世記はとても面白いですね。特に3章への興味は尽きません。しかし、詳しく学んでいる時間が残念なことにありません。結論だけ見ましょう。
主は、人を「エデンから追放」されました。ケルビムまで置いて、二度と戻れないようにされました。
なぜでしょう。
それは「いのちの木への道を守るため」です。つまり、人が二度と「いのちの木」から取って食べることができないようにするためです。
「いのちの木」から取って食べることができるのは「エデンの園に住む者だけ」です。そして「エデンの園」に住むことができる「人」は、「神との交わり」を許された人だけです。
そよ風の吹くころ、主は彼らと語られました。アダムは、主と並んで歩いたのかもしれません。主は、彼らを愛され、親しく語られ、ご自身を啓示してくださいました。それは、素晴らしい時間でした。
アダムとエバが失った最大のものは「神との親しい交わり」です。それこそエデンの園における「一番上等なもの」でした。そして、それこそ「初めの愛」なのです。
彼らは「善悪の知識の木」を選んだときに「初めの愛」を失ったのです。そうして、彼らは「いのちの木」への道を失ってしまいました。
どこから落ちたのか思い出しなさい
エペソの教会は「いのちの木」への道を失っています。
彼らは、いつのころからか気がつかないうちに「初めの愛」から落ちたのです。
いつかは分からないけれど、彼らは「善悪の知識の木」を選んでしまったのでしょう。彼らの教会は立派に奉仕を続けていましたが、それは「神との交わり」から生み出された奉仕ではなかったのです。
愛する兄弟姉妹。
決して「一番上等なもの」を手放してはなりません。それを失うなら「すべて」を失うのです。
サタンは巧妙です。
あなたが熱心な聖徒であるならば「あからさまな罪」をもって誘惑しては来ないでしょう。あなたの心の望みを歪曲した形で実現せよと言って来るでしょう。
つまり「もっと主のために働きたい」という純粋な気持ちに付け込んで来るということです。
「悪に屈服しないぞ」という思いに付け込んできます。「もっと教会を支えたい」という思いに付け込みます。あなたの「熱心」が歪められるように働きかけます。
これは教会に「よくある」現象です。多かれ少なかれ、私たちは「自分の熱心」を「主との交わり」以外に向けているのではないかと思います。
前回、学びましたが「支えておられる」のはイエス様です。私たちは「主の右の手に握られて」います。
すべては、主の御手にあると告白しながら、ついつい私はそれを忘れてしまいます。
「初めの愛」とは「立ち位置」の問題です。エペソの教会は「どこから落ちたのか」を思い出す必要がありました。彼らは立っていたところから「落ちた」のです。そして、彼らは今、イエス様とは「反対の側」に立っているのです。
必要なことは「主のために」ではなく「主とともに」あることです。
イエス様が十字架に架かって血を流してくださったのは、私たちが「主とともに」あるためです。主は、私たちを「取り戻すため」に十字架を忍んでくださったのです。
エデンの東では「ケルビム」が通れないように守っていました。エデンの園への道を守っていました。
幕屋が与えられた時、至聖所への道は「垂れ幕」でふさがれていました。その垂れ幕には「ケルビム」の刺繍が施されていました。つまり、至聖所へは「いつでも」「簡単に」入ることはできなかったのです。
しかし、イエス様がご自分のいのちをかけて「幕」をひき裂いてくださいました。
イエス様は、至聖所への道を切り開いてくださいました。「ケルビム」は、そこをもう守ってはいません。
私たちは、主イエスの血潮によって大胆に恵みの御座に近づけるようになったのです。主は「交わり」を回復してくださいました。
これが「一番上等なもの」です。決して失ってはならない「初めの愛」です。ダビデの求めた「一つのこと」です。
「一つのこと」を求めなくなったならば、それはもはや「教会」ではありません。
立派な会堂があっても、素晴らしい奉仕をしていても、一番上等なものを見失ったならば、そこに「いのち」が流れることはありません。奇跡が起こっていても、素晴らしい賛美が奏でられていても、人が増えていたとしても、そこに「本当のいのち」はありません。
なぜなら、イエス様とは「反対の側」に立っているからです。
主は「初めの愛」をいつまでも覚えておられます。そして、いつまでも「初めの愛」にとどまって欲しいと願っておれます。
主は、イスラエルの「若いころの真実の愛」を覚えていると言われます。
それは、まだ約束の地に入る前のことです。エジプトから脱出し、荒野の旅を続けていた時代のことです。
あのころイスラエルは「不平不満ばかり」言っていました。「食べる物がない」だの「水がない」だの「肉が食べたい」だのと叫んでいました。
とても従順には見えません。しかし、主は、荒野の旅を懐かしく思っておられるのです。
なぜなら、イスラエルは、約束の地に入って安定した生活を送るようになると、自分たちをエジプトから導き出された主なる神を忘れてしまったからです。彼らは、多くの偶像を慕い求め、みな、主なる神から離れてしまったからです。
荒野でのイスラエルは「わがまま」でした。しかし、彼らは「主だけ」を見つめて歩いていました。昼は雲の柱、夜は火の柱を見て過ごしました。神の臨在の幕屋が、常に中心にありました。彼らは、主の導きのとおりに進んだのです。
主は、そのときのことを「ずっと覚えて」おられるのです。主は、彼らと「ともに」旅をしたことを覚えておられるのです。そして、それこそが「主の願われること」だったのです。
「初めの愛」とは「主とともにいる」ことです。主は「ともに歩く」ことを望んでおられるのです。
エノクは、なぜ喜ばれたのでしょう。彼は信仰によって何をしたのでしょう。
エノクが有名なのは、彼が奇跡を行ったからではありません。彼が「何をしたのか」を聖書は詳しく記していません。私たちは、ただ彼が「預言者」であったのだろうなとユダ書によって知るだけです。
エノクの名前が輝いているのは、ただ彼が「神とともに歩んだ」からです。そして、それが人にできる最善最高の生き方なのです。
私たちは、エノクのように生きることができます。いいえ、それ以上かもしれません。なぜなら、私たちのうちには「キリストが生きておられる」のですから。
初めの行いをしなさい
エペソの教会は「落ちた」ことに気が付く必要がありました。そして「悔い改める」必要がありました。
「悔い改める」とは「向きを変える」ということです。
今のままでは、彼らは「イエス様と反対側」に歩いて行くことになります。その先には「滅び」しかりません。いつでもそうです。イエス様と反対側に行って「生きる」ことなどできません。
イエス様は、彼らに「初めの行い」をしなさいと言われました。彼らは向きを変えて「初めの行い」をしなければならないのです。
しかし、すでに彼らは「愛のある行い」をしていました。前回も言いましたが、彼らは「みなし子」の世話を自発的に行っていました。「子捨て場」に捨てられた赤ちゃんを助けていたのです。貧しい人々にも親切でした。
それらは「愛のある行い」ではないのでしょうか?
イエス様は、エペソの教会に対して「わたしは、あなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている」と言われました。主は、彼らの「愛のある行い」をご存知です。
それをご存じの上で「悔い改めなさい」と言われました。そして「初めの行い」をしなさいと言っておられるのです。そうしなければ「燭台を取り除く」と宣告されたのです。
エペソの教会の「行い、労苦、忍耐」は、まるっきり「初めの行い」とは別物だということです。
これは、衝撃的なことですね。私は、自分を本当に省みる必要があります。
主は、思い出して欲しいと願っておられます。向きを変えて、一緒に歩もうと望んでおられます。
主は「荒野に誘う」と言われます。そこで「二人きり」になりたいと望まれたのです。そして「優しく語りかけよう」と言われます。そこで「答えて」欲しいと願っておられるのです。
あの時のように、エジプトから上って来た時のように、ご自身だけを見て欲しいと望んでおられるのです。
主の願っておられることは、創世記の時代から変わっていないと私は思います。
主は「呼べば、答える」という関係を私たちに望んでおられるのです。
「あなたは、どこにいるのか」と問いかければ「はい、私はここにおります」と答えて欲しいと思っておられるのです。
エペソの教会は忙しくなり過ぎたのかもしれません。もしくは、知識や経験が豊富になったので「主を頼らず」にすべてを行えるようにうなったのかもしれません。
彼らは、ある時点において「神に献身する」のではなく「教会に献身する」ようになったのでしょう。
エペソの教会に求められることは「善い行い」ではなく「初めの行い」です。
それは「主とともに歩くこと」です。
「捕らえている」とは、欄外注釈によると「駆り立てている」です。以前の新改訳では「取り囲んでいる」と訳されていました。「押し出される」と訳すこともできます。
私たちは「キリストの愛」によって「駆り立てられる」のです。「取り囲まれて」いるのです。そして、その愛によって「押し出される」のです。ある先生は「ところてんのようなイメージ」と言っていました。
これが使徒パウロの動機です。パウロほど馬車馬のように活動した人はいないように思えます。彼の奉仕の原動力は「キリストの愛」です。パウロは「キリストの愛に駆り立てられて」宣教を行ったのです。
あなたが「キリストの愛」に満たされるなら、駆り立てられるように「行う」でしょう。それが「何か」は分かりませんが、主はあなたを「何か」に駆り立てられます。
愛の応答としての行い
「初めの行い」をしなさいとイエス様は言われます。
それは、あなたが「キリストの愛」に取り囲まれることから始まります。「行い」ファーストではないのです。私たちは常に「わたしを愛しているか」という御声に反応して行うのです。
イエス様は「わたしを愛するか」とペテロに聞かれました。
「この人たち以上に」とは、原語を直訳すると「これらのものよりも」です。
つまり「この人たち」を指しているとも言えますし「大量の魚」を指しているとも言えます。だいたいの訳では「この人たちよりも」という意味で訳されています。
そして、私は例のごとく「どちらでもいい」と思っています。むしろ「どちらの意味も含む」と思っています。
私たちは「この世の何よりも、イエス様を愛するか」と問われていると思うからです。
「大量に獲れた魚」よりも、主を愛するか?
「ここにいる仲間」よりも、主を愛するか?
自分の成功よりも、主を愛するか?
建て上げた会堂よりも、主を愛するか?
私たちの応答は、ペテロのように「弱々しい」かもしれません。一度裏切ってしまったペテロは「もちろん。私はどんなものよりも、あなたを愛します」と断言することはできませんでした。
しかし、それでも、彼の精一杯の思いをイエス様に伝えました。
「ああ、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です」
たとえ「弱々しく」ても、あなたが主に愛を伝えるならば、主はそれを受け入れてくださいます。主は「応答」を求めておられるのです。「呼びかけ」たなら「返事」をして欲しいと望んでおられるのです。
「わたしを愛するか」と尋ねたなら「はい、私は愛します」と答えて欲しいと願っておられるのです。
まず、主との「愛の回復」が必要なのです。主との「会話」が重要なのです。その後、主があなたに「行い」を備えてくださいます。
ペテロには「わたしの子羊を飼いなさい」と命じられました。ペテロは、イエス様への愛の応答として「主の子羊を世話した」のです。
ペテロは、失敗したり失言をしたりして、パウロに怒られることもあったようですが、立派な「牧者」でした。イエス様への愛のかけを一生涯かけて表しました。そして、次の牧者へとバトンをつなぎました。
「自発的に」「心を込めて」
私たちは「初めの愛」を決して忘れてはなりません。もし、落ちてしまったなら、すぐさま向きを変えて、イエス様のもとに走って行くべきです。
イエス様こそ私たちの「初めの愛」なのですから。
「強制されてではなく」「愛によって駆り立てられるように」行うのです。
「主との交わり」「主との愛の関係」がない奉仕は、それがどんなに「成功」していても「立派」であっても、そこに「いのち」はないのです。必ずいつか「廃れて」しまうのです。
主は、エペソの教会に「悔い改め」る機会を与えてくださいました。
この素晴らしい教会を、主は惜しまれたのだと思います。ニネベの町がヨナの宣教で悔い改めたように、エペソの教会にも「悔い改めて」欲しいと願われたのでしょう。
「エペソ」とは「最愛の人」という意味だと言われます。イエス様は、エペソの教会をとても愛されていたと思います。「初めの愛」をもう一度、エペソの教会と分かち合いたいと望んでおられただろうと思います。
現在、エペソの町は「観光地」になっています。遺構しかありません。「アジアの光」と呼ばれ美しい湾岸都市であったのは過去のことです。教会の輝かしい功績も消え失せました。
「過去の栄光」で「いのちを保つ」ことはできません。「初めの愛」は永遠です。私たちは永遠に「初めの愛」にとどまるのです。
さて、今回で「エペソにある教会への手紙」の学びを終了するつもりでしたが、あと6節と7節が残っています。それと「燭台の間を歩く方」にも触れられませんでしたね。我ながら、この進みの遅さにうんざりし始めました(笑)
次回、続きを学ぶか、それとも「スミルナにある教会への手紙」進むか検討中です。
祝福を祈ります。