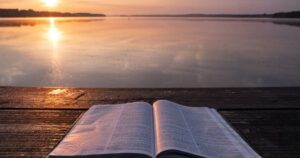黙示録2:1
エペソにある教会の御使いに書き送れ。「右手に七つの星を握ぎる方、七つの金の燭台の間を歩く方が、こう言われるー。
エペソにある教会への手紙
「エペソにある教会の御使いに書き送れ」と、主は言われました。
エペソの教会は「七つの教会」の中で唯一、聖書から背景が分かる教会です。
パウロが「三年の間、夜も昼も、涙とともに訓戒し続けて来た教会」です。パウロが獄中から気にかけて手紙を送った教会です。あの美しい「エペソ人への手紙」を受け取った教会なのです。
ある意味において「エペソの教会」は特別と言えるかもしれません。
パウロに育てられ、のちにテモテ、そして、使徒ヨハネによって監督された教会です。彼らが真理に立って戦えるのは当然なのかもしれません。
使徒の働きに背景を求めつつ学びを進めていきたいと思います。
差出人名は「右手に七つの星を握ぎる方、七つの金の燭台の間を歩く方」です。今回は「右手に七つの星を握る方」を中心に学びます。
「右の手」は「力」を表します。主の右の手は、愛する者を守り支える力強い御手です。また、主の右の手は、敵を打ち倒す力強い御手です。
主は右の手に「七つの星を握って」おられるのです。
ヨハネにお姿を現されたとき、イエス様は右手に星を「持って」おられました。
しかし、今、エペソの教会に告げられたのは、星を「握って」おられるご自身の姿です。「持つ」と「握る」では、少し受ける印象が変わってきますね。
「持つ」は、原語では「持っている」「所有している」「保持している」などと訳せます。
「握る」は「強く掴む」「しっかりと握る」「しっかり保持する」と訳せます。
主は、エペソの教会に「しっかり掴んでいる」「完全に握っている」と伝えておられるのでしょう。主がしっかり握っておられるのは「七つの星」です。
また、イエス様はエペソの教会に「七つの金の燭台の間を歩く方」としても啓示されました。
ヨハネが見た幻では、イエス様は「七つの金の燭台の真ん中」におられましたが、今は、その間を「歩いて」おられます。
「星」と「燭台」の解釈については、イエス様が教えてくださったことに従いましょう。
これには「秘められた意味」があると主は言われます。その意味とは「星」は「教会の御使い」のことで「燭台」は「教会」であるということです。
さて、ここで疑問が湧きますね。「教会の御使いたち」とは、実際には「誰のことか?」という疑問です。
これは、正直に言うと分かりません(笑)
「御使い」と訳されている語は、単に「使者たち」と訳すこともできます。ですから、一般的には「教会の働き人たち」を指していると解釈されます。
ただ、この箇所だけを「使者たち」と訳して、その他の個所は「御使い」とするのは釈然としないという意見もあります。定冠詞の有無など、何やら難しいことが議論されていますが、まあ、よく分かりません。
主の御目には、私たちが見て知っている「教会」ではなくて、もっと何か「違うもの」が映っているのかもしれません。
初代教会では、御使いは、もっと身近に感じられる存在だったようにも思います。「使徒の働き」を読むと、確かに御使いが活躍しているのを確認することができます。私は、私たちが礼拝をささげる時には、御使いもいて一緒に礼拝しているのかもしれないなと思います。
しかし、この場合「御使いを右手に握っておられる」とするのは、何となくしっくりこないので「教会の働き人たち」「指導者たち」を表すという解釈の方がよいのかなと考えています。
まあ、ここは深入りせずに先に進みましょう。それでなくても、なかなか進んでいないのですから(笑)
どちらにしても、イエス様が「教会」に関心を持っておられ、聖徒を握っておられ、私たちの間を歩いておられるのだということは確かなことです。
エペソという町について
エペソという町について古代の学者は「アジアの光」「アジアの虚栄の市」「ローマの門戸」などと呼んでいます。
エペソは、その地方の首都ではありませんでした。当時の首都はペルガモンです。しかし、実質は「アジア最大の都市」でした。
エペソは「商業」と「宗教」の中心地でした。すべての「良い商品」がエペソの港に運ばれてきたのです。
バーノン・マギー神学博士は、パウロが初めてエペソに来た時、大理石で舗装された道を見ただろうと言っています。エペソは「虚栄の市」と呼ばれているように、豪華な町だったようです。彼らは栄えていました。
パウロはエペソで「獣」と戦ったと言っています。それはエペソでの戦いの激しさを物語っています。
使徒の働き19章には、エペソでの騒動のことが記されています。
その箇所を読むと、エペソの人々の生活に偶像が根深く関係していたことが分かります。
はっきりと記されていますね。彼らは「繁盛して」いました。かなり儲けていたのです。
エペソのアルテミス神殿は、現在は遺構のみとなっていますが、当時は「世界七不思議のひとつ」と呼ばれるほど壮麗な建物でした。一説によると、アテネのパルテノン神殿の4倍ほどあったと言われています。
アルテミスの神殿は、縦が100メートル、横が30メートル、高さが15メートルと、諸国の王たちが献上した大理石の柱がなんと127本も連なり並べられていたといいます。異様な偶像、闇の力があからさまに見えるエペソの町です。人口30万人。そして二万五千人は入るといわれるコロセウムをもつエペソの町です。
黙示録の七つの教会への手紙 柴田敏彦著 いのちのことば社
彼らは「ぼこぼこした塊りがついた石」をアルテミスの神体として祭っていました。しかし、エペソの人々にとっては、アルテミスそのものよりも「神殿」の方が大切であったように私には思えます。
アルテミスとは、セレナ、ディアナ(ダイアナ)などとも呼ばれます。当時の人々は、エペソのアルテミス神殿を聖地として巡礼に来たようです。
ゆえに当時の神殿は「宗教施設」と「観光所」をかねたようなものでした。神殿には絵画も描かれていたようですから「美術館」であったとも言えます。
偶像の祭司が仕えていました。祭司という名の娼婦や男娼です。神殿では、儀式と称して不品行が堂々と行われていました。言葉にすると気分が悪くなるような汚れたことが、日々、行われていたのです。
また商売人もいました。彼らは、そこにお参りに来る人々の両替を手伝ったり、土産を売ったりしていました。神殿の模型はとてもよく売れたようです。もちろん飲食店なんかも繁盛していたことでしょう。
エペソの人々の中心にはアルテミスの神殿があったのです。それは彼らの技術の結晶であり誇りでした。そして、彼らの生活に深く関わるものでした。それが失われると生計が立たなくなる人が大勢いたのです。
ああ、パウロはこのような町で伝道していたのです。多くの「獣」たちがいたことでしょう。戦いが激しかったことにも納得がいきます。
しかし、主の恵みはエペソの町にも注がれました。
主は、パウロをとおして驚くべき力あるわざを行われました。人々の病は癒され、悪霊は追い出されたのです。
それを真似したスケワという祭司長の息子七人が、悪霊追い出しを行ったところ、逆に返り討ちに会うという事件が起こります。このことが、みなに知れ渡り、多くの人がイエス様を信じるようになったのです。
エペソの教会の人々が「信仰に堅く立って」いることが分かります。彼らは「断ち切り」ました。自分の罪を告白し、悪しき者との縁を切ったのです。
ゆえにエペソで大暴動が起こったとも言えます。
それでも、エペソの教会は立ち続けました。彼らは戦う教会です。そして、彼らは負けませんでした。
主はエペソの教会を称賛されます
主は、エペソの教会の「行い、労苦と忍耐を知っている」と言われました。一言で表すなら彼らは「素晴らしい教会」です。
パウロは、エペソの教会の長老たちへの別れの言葉の中で、こう述べました。
まさに、そのとおりのことが起こりました。
エペソ教会は、パウロの教えを心に留めていました。しっかりと立ちました。偽使徒を見破りました。彼らは、騙されませんでした。荒らす狼を撃退しました。立派な教会です。
使徒ヨハネは「霊をすべて信じてはいけません」と言っています。
これは、今の時代にあっても大切な教えです。何でもかんでも「良さそうなもの」に飛びついてはいけません。
聖霊様のことを語っているからと言って「すべて信じて」はいけません。
「吟味しなさい」と聖書は言っているのです。つまり、私たちは「吟味すること」ができなければならないのです。
そのためには、まず、私たち自身が「真理に立って」いる必要があります。私たち自身が「主とともに」いる必要があるのです。
エペソの教会は、この点において称賛されています。
彼らは「悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いた」と言われています。
パウロは「偽使徒たち」のことを「あの大使徒たち」と言っています。
コリントの教会において「偽使徒」は、パウロよりも立派な「大使徒」として扱われていたのでしょう。
「偽使徒たち」は立派に見えたのです。話し方が上手くて、すっかり信じてしまったのです。コリントの教会は「偽使徒たち」に陶酔してしまいました。完全に受け入れたのです。
しかし、エペソの教会は違いました。彼らは「偽使徒」を見破りました。悪者たちに我慢しませんでした。異なる教えを断固として拒否しました。
終わりの時代には、多くの惑わす者が現れます。
イエス様は「惑わされないように気をつけなさい」と言われました。
なぜなら、主の御名を名乗る者が大勢現れるからです。
パウロは「あなたがた自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分たちのほうに引き込もうとする者たち」が現れると言いました。
私たちは「惑わされないように気をつけて」いなければなりません。
惑わされないためには「人」や「現われ」で判断しないことです。
「あの人が言っているから本当だ」
「奇跡が起こったのだから聖霊様だ」
見えるところによって判断してはなりません。
私たちは、真理に立ちましょう。「教えの風」に吹き回されたり、もてあそばれたりしないように、キリストにあって成長することを切に求めましょう。
この点において、エペソの教会は私たちが見習うべき模範と言えます。
イエス様はエペソの教会を誉められたのです。
主が支えておられます
主は言われます。
イエス様は、エペソの教会がどれほど戦ってきたのかすべて知っておられます。そして、その戦いが「御名のため」であったこともご存知です。
彼らの「行い」を主は認めておられます。彼らが「労苦」していることを知っておられます。彼らの「忍耐」を主はご存知なのです。
エペソの教会の「行い」は良いものでした。
古代ローマに「子捨て場」があったことは有名です。当時ローマ帝国の支配下にあったエペソの町にもそのような場所がありました。望まれずに生まれた赤ちゃんを捨てることは合法だったのです。
エペソの聖徒たちは、そのような境遇の子どもたちを救い出して養っていたようです。彼らの行いは称賛されるべきものです。人々は、彼らには愛があると言っていたでしょう。
「労苦」と訳された語は「骨折り」とも訳せます。原語には「まさに力尽きて倒れんとするばかり」という意味が含まれています。
すべての力を振り絞って「主の御名のために」労苦していたエペソの教会の姿が見えるようです。
しかも、彼らは「疲れ果てて」はいませんでした、
彼らは「忍耐」していたのです。これは「我慢」という意味ではありません。ここでいう「忍耐」には「底の方に希望を感じさせる忍耐」です。
彼らは「自分のために」に耐え忍んでいたのではありません。
主は「わたしの名のために耐え忍び、疲れ果てなかった」と言っておられます。
このような立派な教会に、イエス様は「右手に七つの星を握ぎる方」としてご自身を啓示されました。
主は「わたしが握っているのだ」とエペソの教会に伝えられたのです。
なぜ、主はわざわざ「握っている」「掴んでいる」ということを強調されたのでしょう。それは、彼らにとって、とても重要なことだったからだと推測できます。
つまり、簡単に言えば「あなたを握っているのは誰か」ということを知らせておられるのです。
私たちは時々間違ってしまうのです。
「教会のために頑張らなければならない」と思ってしまいます。
「教会を支えなければならない」とも思います。
しかし「教会」とは、何なのでしょう?
もちろん「建物」ではないのは当然のことです。
しかし、正直に言うと、私は一時期「会堂の賃貸料」を満たすために働いていたことがあります。今から思えば、とっとと引き払えばよかったのです。
世の中で働くことは、特に嫌ではありませんでした。もちろん、辛い時もありました。しかし、それでも楽しく働いていた方だと思います。「献金、献金」と教会のメンバーにまくしたてるより、自分が働きに出た方がよっぽどいいよねと私は思っていたのです。
しかし、それは間違った考えでした。その考えは「高慢」です。
誤解しないでください。働くことが「悪い」と言っているのではありません。私は世の中で働いて、お金を稼ぐことが悪いなどと、これっぽっちも思いません。
私が言いたいのは「自分が教会を支えなければならない」という心のことです。
「教会」とは何でしょう?
「教会」は建物ではないし、集会のことでもありません。「教会に行こう」というのは厳密に言えば間違っているわけです。
「教会」とは「あなたと私」のことです。
二人でも三人でも、主の御名において集まっているなら、そこが教会です。イエス様はそこにおられます。
百人集まろうと、千人集まろうと、1億円の立派な会堂だろうと、主がそこにおられないなら教会ではないのです。
覚えてください。
教会に集うのではありません。あなたと私が、二人だけでも集まるならば、そこに教会は「ある」のです。
私が「教会を支える」のではありません。イエス様が「私を支えて」くださるのです。
牧師が教会を「支える」ことなどできません。献身者は「教会を支える」者ではありません。
私たちは、みな「生きた供え物」です。私たちは「主の御手に握られて」います。主が「教会である人々」を「しっかり掴んで」おられるのです。
行いでいのちを保つことはできません
「行い」は必要です。恵みに生かされる聖徒は「良い行い」に歩むものです。しかし、大切なことは順番です。
すべては「恵み」です。いつも「恵み」から始まるのです。
救いは「行い」によるのではありません。
「行い」によって「教会」を支えることはできません。
「行い」によって「教会になる」こともできません。
私たちは「行い」によって「いのち」を保つことはできないのです。
教会であり続けるために「会堂」は必要ではありません。教会であり続けるために「何か」を行う必要はありません。
エペソの教会の「行い」「労苦」「忍耐」は立派でした。しかし、それらは称賛はされますが「いのち」を保つ役には立たないのです。
私たちは「恵み」のゆえに「信仰」によって救われました。
そして、その原則はどんなときにも有効なのです。
「良い行い」は、主が望まれることです。つまり「みこころ」です。
そして、主はみこころを成し遂げられる方です。
つまり私たちは「良い行い」をするようにされるということです。
私たちは「何が良い行いなのか」を捜す必要すらありません。恵み深い主は、ちゃんと私たちが「良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えて」くださっているからです。
私たちは救われました。いのちを持っています。すでに聖徒です。私たちは教会です。
聖徒であり続けるために「良い行い」をするのではありません。
いのちを保つために「良い行い」をするのではありません。
私たちは「すでに聖徒であり、いのちを持っているので」良い行いに歩むのです。しかも、あらかじめ備えられた良い行いに歩むのです。
すべては、主の御手の中にあるのです。
支えられているのは「私」です。
握っておられるのは「主」です。
そして、主は「完全」に握っておられます。
心配することはないのです。何が起こっても、何も起こらなくても、私たちは「完全」に握られていることに安心しておればよいのです。
次回は「教会の間を歩く方」と「はじめの愛」について学びたいと思います。
祝福を祈ります。