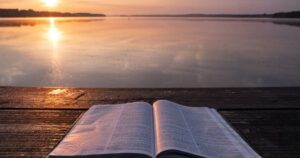黙示録2:10
あなたがたが受けようとしている苦しみを、何も恐れることはない。見よ。悪魔は試すために、あなたがたのうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなたがたは十日の間、苦難にあう。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば、わたしはあなたにいのちの冠を与える。
何も恐れることはないと言われます
イエス様はスミルナの教会に「あなたがたは苦しみを受けようとしている」と言われました。
その苦しみとは「だれかが牢に投げ込まれる」ということです。
つまり、迫害が激しくなるということです。
「見よ。悪魔は試すために、あなたがたのうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。」
悪魔はスミルナの教会を試そうとしています。
この迫害は無傷ではすみません。誰かが「投獄」されるのです。
ここで「悪魔」と訳されている語は「ディアボロス」と言います。
「ディアボロス」とは「訴える者」という意味です。「中傷する者」とか「讒言(ざんげん)者」という意味もあります。
「讒言(ざんげん)」とは、広辞苑にはこう書いてあります。
人をおとしいれるため、事実をまげ、また偽って(目上の人に)その人を悪く言うこと。
広辞苑第七版
「目上の人」に「ありもしない告げ口をする人」を「讒言者」と言うのです。
悪魔は、主の御前に出て、私たちを「訴える者」です。確かに、「讒言者」と呼ぶにふさわしい存在ですね。
ちなみに、前回、学びましたが「サタン」とは「反対する者」「敵」という意味です。
私たちの敵は、私たちを訴える者なのです。
その昔、サタンはヨブを落としれるために、主に訴えました。
サタンは、ヨブの忠実さは「主の祝福」のおかげだと言いました。もし、祝福が取り去られたならば、ヨブは必ず主を呪うに違いないと訴えました。
おそらく、スミルナの教会も同じように訴えられたのだろうと私は思います。
スミルナの教会も「忠実さ」を試されたのです。
「十日の間、苦難にあう」とイエス様は言われました。
「十日の間」が、何を意味するのかは正確には分かりません。
文字通り「十日間」の意味かも知れません。「10年の意味だ」という学者さんもいます。
「10」は完全数と呼ばれる数字の一つです。「12」や「7」なども完全数と呼ばれます。ですから「十日の間」とは「完全な苦難」という意味だとも言われます。
十日の苦難は(一日が一年として)単に十年を意味するだけではなく、十割、すなわち百パーセントの苦難をも意味します。
黙示録の中のキリスト W・E シューベルト著 リバイバル・フェローシップ(軽井沢聖書学院)
「十日間」の正確な意味はわかりませんが、いずれにしても「期間が定められている」ということです。
その苦難がどれほど激しくても、そして、思った以上に長がったとしても「必ず終わる」ことだけは確かなのです。
これは「悪魔の仕業」です。
「悪魔は試すために、あなたがたのうちのだれかを牢に投げ込もうとしている」とイエス様は言われました。
これは「悪魔からの試み」です。
しかし、その「試み」を許可されたのは主なる神です。この「試み」を最終的に支配しておられるのは、主なる神であるということです。
ですから、イエス様は言われるのです。
「あなたがたが受けようとしている苦しみを、何も恐れることはない」と。
スミルナの教会を苦難が襲います。それは避けることができません。主は、そこから「逃がしてあげよう」とは言われませんでした。
それどころか逆にこう言われます。「死に至るまで忠実でありなさい」と。
「死に至るまで」とは、つまり、スミルナの苦難の先には「死」があるということです。
スミルナの教会に待っているのは「苦難」です。そして、その「苦難」の先には「死」があります。
しかし、イエス様は言われます。
「わたしは、初めであり終わりである。死んでよみがえった者である」
スミルナの教会の希望は「初めであり終わりである方、死んでよみがえった方」にあります。
主は、スミルナの「十日間」の初めから終わりまで、すべてを支配しておられます。目の前で、サタンが大暴れしている姿を見たとしても「この世のあの者」よりも強い方がおられるのです。
スミルナの教会は「死」の先を見ることができました。「苦難」の先、「死」の先に「いのち」があるのです。彼らは「よみがえられた方」を見て進みました。
「何も恐れることはない」と言われた方を見つめて進んだのです。
迫害下にあった2世紀以降の教会の姿です
さて「十日の間」の意味については、もう一つ解釈があります。
ローマ皇帝の時代はこの後も続きます。
10人の皇帝が、約250年にわたって、キリスト教徒を迫害するという時代が続きます。「十日の間」とは、10人のローマ皇帝が迫害していた時期を表すと言われています。
その期間は、ネロ(BC54~68)からディオクレティアヌス(BC303~313ごろ)までの約250年です。
皇帝ネロの名前は聞いたことがありますね。パウロを断頭し、ペテロを逆さ十字架につけたとされる皇帝です。
そのネロよりも、もっと残虐だったのが最後の皇帝ディオクレティアヌスです。彼は「最悪の迫害者」と言われました。最後が一番激しかったのです。この250年間、キリスト者は迫害され続けました。迫害は、激しさを増すように見えました。それは、終わらないように思えたでしょう。
「十日の間」について、この解釈が正しいかどうかはわかりません。けれど、スミルナの教会が迫害下にあった2世紀から3世紀の教会を現わしているのは確かであろうと思います。
このようにスミルナの教会は、苦しみ、貧しさにある、迫害下にある教会であることがわかります。初代教会を表すエペソの教会の次に、二、三世紀に起こったローマ帝国による大迫害時代の教会を表していると言われます。つまり、三一三年のミラノ勅令による、キリスト教のローマ国教化までの教会を現わしているのです。
世の終わりが来る! 奧山実著 マルコーシュ・パブリケーション
ジョン・フォックスの「殉教者列伝」によると、この250年間に「500万人」の聖徒が殉教したと言われています。
その時代の人々が、スミルナの教会への手紙が「迫害下の自分たちを表す」ことを知っていたかどうかはわかりません。しかし、彼らは「スミルナの教会」に自分たちを重ね合わせたことだろうと思います。
彼らにとっても「初めであり終わりである方。死んでよみがえった方」は希望そのものであったに違いありません。
「殉教者の血」は「教会の種」だと言われます。多くの一粒の麦が地に落ちました。
彼らはみな「死に至るまで忠実であった」人々です。
悪魔は、彼らを試みました。彼らの「忠実さ」を試しました。
ヨブのように、彼らは「すべて」を失いました。家財や愛する人を失いました。
そして、彼らはヨブ以上に試されました。住む場所を追われ、そして「自分のいのち」までも奪われました。
彼らの多くは密告され捕らえられていきました。信じていた人に裏切られた聖徒もいます。
この「十日の間」は、大患難の期間をあらわすものではありません。これは、大患難の三年半とは関係がありません。大患難の時、地上は「激しい苦難」に襲われますが、それは悪魔の仕業ではありません。
悪魔は、自分の時が短いことを知って暴れまわります。しかし、悪魔が暴れ回ることが大患難なのではありません。勘違いしてはなりません。大患難のときに注がれるのは「神の怒り」です。そして、その時、私は地上にいないと信じています。
聖徒は、患難期でなくても苦難にあいます。しかし、それは「神の怒り」ではありません。悪魔は、聖徒の忠実さに挑戦してきます。しかし、神は苦難にある聖徒とともにおられます。
主は必ず守ってくださいます。必ず救ってくださいます。しかし、それは私が想像する方法とは違うかもしれません。
迫害下において信仰を保ち続けた聖徒たちは、このイエス様のことばを「現実」として実感したでしょう。
彼らは「ご利益信仰」ではありませんでした。彼らは「失うならば得る」ということを身をもって体験していました。あえて言うならば「失うために信じた」のです。「失うならば得る」からです。
250年もの間、迫害され続けたのに聖徒は撲滅されませんでした。それどころか、彼らは地下で集会を持ち、それでも伝道を続け、新しい聖徒が加わっていきました。
そのような状況下で「イエスは主です」との告白は「死」を招くようなものです。彼らは「自分のいのち」を失ってでも「キリストのいのち」が欲しかったのです。
私たちは「失う」ことを恐れます。不安に思います。まだ失ってもいないのに「失ったらどうしよう」と怯えています。しかも、私たちが「失うかも」と恐れているのは「いのち」ではないのです。
仕事を失うかもと恐れます。明日の食べる物について思い煩います。着る物について悩みます。多くの思い煩いが、私の中にはあります。しかし、それらは「いのち」を奪われるような苦難ではありません。
私たちは「祝福」について勘違いしているのです。「快適な生活」が「豊かないのち」の証拠であると誤解しているのです。「失う恵み」があるのです。「失って得る」ものこそ本当の豊かないのちなのです。
もし「豊かさ」が目に見えることだけで量られるなら、スミルナの聖徒は世界で一番みじめな人々です。実際に彼らは「極度に貧しい」状態にあったのですから。
しかし、イエス様は言われました。「だが、あなたは富んでいる」と。
迫害下にある教会は「貧しく」見えます。しかし、彼らは常に「賛美」をしています。
「賛美」とは、主を認めることです。どのような状態にあったとしても「変わらない唯一の方」を認めて告白することです。
主よ、あなたは恵み深い方です。
主よ、あなたはすべてを治めておられます。
彼らの心には「豊かに」主ご自身があふれていました。彼らは「豊かに」主ご自身を知っていました。
スミルナの大競技場で多くの聖徒が殉教しました。ある者は獅子の餌食とされ、ある者は火あぶりにされました。
AD155年、スミルナの教会の監督であったポリュカルポスも火あぶりの刑に処されました。
「誓え、誓ったら釈放してやろう。キリストを否定せよ」という総督のことばに耳をかたむけませんでした。
ポリュカルポスは言いました。
私は八十六年間もキリスト様にお仕えして参ったが、ただの一度たりとも、キリスト様は私に対して不正を加え給うようなことはなさらなかった。どうして私が、私を救い給うた私の王を冒瀆することができようか。
ポリュカルポスの殉教 使徒教父文書 荒井献編 講談社
ポリュカルポスの処刑の前に罪名が大声で叫ばれました。総督は、伝令に三回も叫ばせたそうです。
「ポリュカルポスは、自分からキリスト信者であると告白した」
これを聞いて大競技場に集っていた群衆は「激怒」したと言われます。怒った群衆は「獅子に襲わせろ」と要求しました。けれど、時期的に「野獣の競技」は終わっていたので、ポリュカルポスは火あぶりに処せられたということです。
ポリュカルポスの罪名は、群衆を激怒させました。しかし、主は群衆に「激怒」されたでしょう。
火をつけられる前、ポリュカルポスは天を仰いで祈ったと言われます。
このゆえに、一切のことについて、汝の愛したもう御子、永遠にして、天上にいますイエス・キリストによって、汝をほめたたえます。
ポリュカルポスの殉教 使徒教父文書 荒井献編 講談社
彼の最後の祈りは「賛美」でした。彼だけではなく、多くの殉教者が「賛美」をささげながら召されて行きました。
多くのものに囲まれて、少しの不足に不平をこぼす私と、何も持たず文字通り「そなえもの」となった聖徒たちと、どちらが本当に「豊か」なのでしょう。
どのような状況にあっても、何もかも失っても、それでも「賛美」をささげる心こそ「豊かないのち」に満ちあふれているのです。
いのちの冠を与えると言われます
「死に至るまで忠実」であった聖徒には「いのちの冠」が与えられます。
「いのちでできた冠」ということです。
この「冠」という語は「王冠」を意味するものではありません。
この「冠」は、「花輪(リース)」のことです。姉妹たちは、子どものころ「花冠」をシロツメ草などで編んだことがあるでしょう。これは、そのように「いのちで編まれたリース」のことです。
スミルナの大競技場では、さまざまな競技大会が行われました。そして、その勝者には「リース」が被せられたのです。
聖徒は、大競技場で見世物のように処刑されました。彼らは群衆の怒号が響く中、天に召されていきました。
群衆は「馬鹿な奴らだ。負け犬だ」と聖徒を罵ったでしょう。この世は、聖徒を罵詈雑言で送り出します。
しかし天は、殉教者を、御使いの歌声と「勝利者の冠」で迎えます。聖徒の頭には「いのちで編まれたリース」がのせられるのです。
スミルナの教会に与えられた約束は「いのち」でした。
聖徒は「第二の死」によって害を受けることはありません。
私たちは「一度」死にます。携挙されるなら死ぬことはありません。私たちは「第二の死」によって害を受けることはありません。
しかし、イエス様に従わない者は「第二の死」を経験することになります。
ポリュカルポスは、尋問されたとき「悔い改めないなら火あぶりだ」と脅されたそうです。
彼は「良いことから悪いことに悔い改めるなんてありえない」と一笑に付したあと続けて言いました。
貴下は、ほんの一時燃えてじきに消える火などを持ち出して私をおどかしたつもりになっておられるが、来たるべき未来の審判の火を御存知ないのであろうな。
ポリュカルポスの殉教 使徒教父文書 荒井献編 講談社
「ほんの一時燃えてじきに消える火」と、彼は「火あぶり」をこのように表現したのです。そして、「火あぶり」よりも、もっと恐ろしい「未来の審判の火」があるのだと言ったのです。
私たちは何を恐れるでしょう。本当に恐れるべきものはなんでしょう。本当に喜ぶべきものはなんでしょう。
確かに私たちは「燃えさかる試練」を経験するでしょう。私たちの人生において何らかの試練は必ず起こります。それは「思いがけないこと」ではないのです。
しかし、どれほど「燃えさかって」いるように思えても、その火は必ず消えます。「十日の間」の具体的な意味は分からなくても「期間」が区切られていることは確実です。
私たちの苦難は「一時」なのです。
この世は「すべて」ではりません。サタンのもたらす「試み」は、この世においてだけのことです。
私たちには「その先」があるのです。
私たちには「苦難の先」にもたらされるものがあるのです。
その先を見ましょう。「一時」ではなく「永遠」を見て生きるのです。
見えているものは「すべて」ではありません。この世は「すべて」ではありません。
イエス様は言われます。
「死に至るまで忠実であれ」と。
私たちに求められているのは、ただ「忠実」であり続けることです。
「死」は恐ろしいですね。けれど、それは「終わり」を意味しません。
あなたの状況は「絶望」に見えますか。しかし、それは「終わり」ではありません。
私たちにはいつも「その先」があります。
本当に「その先」などあるのだろうか、と不安に思う気持ちはよく分かります。それでも、私たちは信じましょう。
私たちには「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」がおられます。
ただ、この方に忠実に、どんな苦難を通ったとしても、ただ忠実でありましょう。
その先には「いのちの冠」が待っています。私たちの主が「よくやった。よい忠実なしもべよ」と言ってくださるときがきます。主の釘を打たれた御手をもって「いのちの冠」をかぶせられるときが必ず来ます。
私たちは、その日まで一緒に信じ続けましょう。励まし合いながら従い続けましょう。
私たちの主、「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」にとこしえに栄光がありますように。
祝福を祈ります。