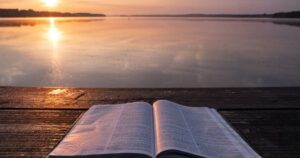黙示録2:8
また、スミルナにある教会の御使いに書き送れ。初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方が、こう言われるー。
初めであり終わりであり、死んでよみがえられた方から
イエス様は、スミルナの教会に「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」としてご自身を啓示されました。
スミルナの教会への手紙は、七つの教会の中で「最も短い」ものです。
ある人は言いました。
「死んでいく者に多くの言葉はいらない。スミルナへのことばは少ない。しかし、最も慰めに満ちている」と。
スミルナの教会には「非難のことば」はありません。彼らは叱責されません。彼らには「励まし」があるだけです。
スミルナとは、現在のトルコ西部の都市「イズミル」のことです。エペソは「アジアの光」と呼ばれましたが、スミルナは「アジアの美」または「アジアの冠」などと呼ばれたようです。現在もその美しさは健在で「エーゲ海の真珠」と呼ばれています。「トルコの大阪」などと呼ぶ人もいます。
「初めであり終わりである方」がスミルナの教会を励まされます。
「初め」とは、エペソの教会に言われた「初めの愛」と同じ語が使われています。つまり「一番上等な」「最も良い」という意味です。
主こそ彼らの「初め」です。一番良いものです。すべてのすべてです。
「終わり」とは「一番端」「最後の」という意味です。主は、空間においても、時間においても「端から端まで」すべてを満たしておられます。
スミルナの教会にとって、イエス様は「初めであり終わり」です。初めからおられ、そして最後に登場されます。私たちは「初めに」この方と出会い、そして「最後に」この方に至ります。
彼らは「最もよい方」を持っています。「最もよい方」で満ちています。彼らの「時」は最初から終わりまでイエス様の御手の中にあります。彼らの存在している空間の端から端まで、主の臨在で満ちています。彼らが生きる「時」の初めから終わりまで、主が支配しておられます。
イエス様は、スミルナの教会に「初めであり終わりである」というご自身を覚えて欲しかったのです。
主はまた「死んでよみがえられた方」としてご自身を啓示されました。これは、すぐにスミルナの教会の経験となるからです。
以前の新改訳では「死んで、また生きた方」と訳されています。
イエス様は死なれました。イエス様は「死」を知っておられるのです。主は、人に起こる「最悪」を経験されました。裏切られ、拒絶され、痛めつけられ、血を流され、死なれたのです。
イエス様はよみがえられました。「死んで、また生きた」のです。そして、今もなお「生きておられる」のです。
スミルナの教会にとって「死んで、また生きた」と言われるイエス様が何よりも必要でした。
よみがえられたイエス様を見て、「死は決して終わりではない」ことを彼らは心に刻み付けました。「死」の先に「生きる」ことがあると彼らは信じました。
イエス様が「生きておられる」ことを彼らは信じました。そして、死を超えた先に「永遠のいのち」があることを信じました。主が生きておられるように、自分たちも「生き続ける」ことを信じたのです。
イエス様は、彼らが「ご自身とひとつ」であり「ご自身の足跡をたどっている」のだと教えたかったのでしょう。
スミルナの教会への手紙は短いけれど、主が「同志」に書き送っているような感じを受けます。なんだかイエス様が「わたしの兄弟たちよ」と呼びかけているような、そんな風に思えるのです。
何を信じて生きるのかが問われているのです
スミルナの町は全体として繁栄していました。スミルナの人々は富んでいたのです。
しかし、スミルナの教会は違いました。主にある聖徒たちは「苦難と貧しさ」の中にいたのです。
「苦難」とは、「押しつける」という意味です。重力がかけられて押しつぶされそうな状態のことです。スミルナの教会は、苦難によって押しつぶされそうになっていました。彼らは精神的に参ってしまうような状況に置かれていたのです。
「貧しさ」とは、原語では「極度の貧しさ」「物乞いをするほどの貧しさ」という意味です。スミルナの教会は物質的にも困窮していました。それは「極度の貧しさ」です。今日の食事にも困るような有様だったのです。
彼らは文字通り「何もかも」を失いました。彼らにとって「キリストを信じること」とは「すべてを失うこと」と同じでした。
「押しつぶされそうな苦難」そして「極度の貧しさ」
目の前に、耐え忍びながら暮らす人々を見て、誰が「私もそうなりたい」と願うでしょうか?
スミルナの聖徒には「世の富」は与えられません。自分の好きな仕事をすることもできません。いわゆる「成功者」にはなれません。
皇帝礼拝を拒むならローマの保護は受けられません。彼らの「家財」が奪われても、殴られて怪我をしても、国の助けを受けることはできません。
ギルド(職業組合みたいなもの)に所属することができないので、仕事は干されます。
しかし、スミルナの聖徒たちは伝道をしました。そして、救われる人々が与えられました。彼らは「何を見て」信仰を告白したのでしょう。
彼らは「キリスト」を見て信仰を告白しました。
「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」を信じたのです。
私は、自分を省みて本当に情けなく感じています。
「十字架につけられたキリスト」以外、いったい何が必要なのでしょう?
宣教のために「あれやこれや」と知恵を絞ることは大事なことでしょう。しかし「福音の安売り」のような宣教は、もう改めなければなりません。
「神は愛です」と伝えることは必要です。それは真理ですから。でも私たちは「神の愛の一部しか」伝えていないように思います。
「イエス様を信じれば救われます」とは、もちろんその通り。
「イエス様はあなたを愛しておられます」それもその通り。
「主は癒し主です」
「主は豊かに与えてくださいます」
「主は平安をくださいます」
すべてもちろん「そのとおり」です。しかし、また同時に「自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従って来なさい」とも言われたのです。それは「神の愛の招き」です。
イエス様は言われました。
私たちは「弟子」をつくらなければなりません。イエス様と同じように「弟子」を集めなければなりません。
イエス様が弟子を呼び集められたとき「信じれば幸せになれるよ」とは言われませんでした。
「信仰の告白」とは「献身の告白」と同じであると私は思います。
「献身」とは「教会で働くこと」という意味ではありません。「信じる」とは「従う」ことです。従わないなら信じていないのです。「信じています。でも…」と言うなら信じていないのと同じなのです。
私の牧師は、すぐに信仰告白をさせない人でした。これは賛否両論あるかと思いますが、必ず「代価」を量らせよと言いました。
つまり、現実的に「起こりそうなこと」をはっきり伝えよと言うことです。
その人が結婚しているならば、夫もしくは妻が反対したならどうするかと聞きます。その人が学生なら、両親が反対して学費を出さないと言ったらどうするかと聞きます。
もちろん、主が必ず支えて助けてくださることも伝えます。両方をきちんと伝えるのです。
そして、その上で「信じます。従います。」と言う人にだけに洗礼を授けました。
私は、そのような教会で育ったのです。にも関わらず、妥協している自分を認めざるを得ません。ある意味において「安売り」をしてしまったことを認めざるを得ません。教会の抱える問題は、ほとんどの場合「福音の安売り」が原因なのではないかと思います。
すべての聖徒が「網を捨てて従った」ならば、起こらない問題が多くあると思うのです。すべての聖徒が「キリストの弟子」であるならば、教会はもっと活動的になります。すべての聖徒が「自分を捨てて従う」ならば、教会は「いのちを得る」ようになります。
私たちが信じているのは何でしょう?
「物」が与えられることですか。
「事」がうまく運ぶことですか。
「物と事」に目を向けているなら、私たちは必ず失望します。それが、たとえ「主の御名」のゆえに求めている「物と事」であってもです。
私たちは「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」を見ます。十字架に架かられたキリストを見ます。死んで、また生きた方を見ます。
それ以外に何が必要でしょう?
この方こそ「すべて」であるという告白だけが、本当の「信仰告白」なのです。そして、この方こそ「すべて」と告白する人は「すべて」を持っているのです。
ゆえに、イエス様は言われます。
「だが、あなたは富んでいる」と。以前の新改訳では「実際には富んでいる」と訳されています。
彼らは「実際には富んでいる」のです。
スミルナの聖徒たちの「実際の姿」を世の人々は認めないでしょう。
スミルナの聖徒が「私たちは富んでいる」と叫んだとしたら、世の人は「頭でも打ったのか?」と言うでしょう。もしくは「負け惜しみ」だと思うでしょう。
しかし、言わせておけばよいのです。私たちは「十字架につけられたキリスト」を宣べ伝えればよいのです。
十字架のことばは「愚か」に見えるのです。しかし、救われる私たちには「神の力」です。
いつでもそうなのです。
人々はイエス様を「あざけり」ました。馬鹿にしたのです。しかし、主の愚かさは「人よりも賢い」のです。そして「神の弱さは人よりも強い」のです。
私たちは「自分がどのように見えるか」に囚われてはなりません。「何もない」こと、もしくは「何かを持っている」ことに目を留めてはなりません。
「貧しく」見えてもいいではないですか。
「弱く」見られるのは嫌ですか。
「愚か」だと言われると腹が立ちますか。
「誤解される」のは辛いですよね。
「こんなことでは証しにならない」と思うでしょうか。
今すぐ、目を「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」に向けましょう。
私たちが証するのは「十字架につけられたキリスト」だけです。
私たちが「悪評」を受けても「好評」を博しても、そんなことはどちらでもよいのです。人が何と言おうとも、私が「キリストのしもべ」であることに変わりはありません。
スミルナの教会は、まさにこのように生きていました。私もまた、このように歩むべきなのです。
ののしられていることも知っている
スミルナの苦難の一つは「自称ユダヤ人たち」から「ののしられる」ことでした。
「ユダヤ人だと自称している」ということは、彼らは「実際にはユダヤ人ではない」ということですね。
ここは2つの意味に解釈できます。実際にユダヤ人でなかったか、もしくは、主が「ユダヤ人」であるとみなされなかったかということです。
実際にユダヤ人でなかったとすれば「ユダヤ教に改宗した異邦人」ということになります。
「日本人だと自称しているが、実際には日本人ではない人々」は、日本人でしょうか。外人が日本人だと詐称しているだけで、実際は日本人ではありませんね。これは神学ではなく国語の問題です。~中略~これはユダヤ人のふりをしている異邦人なのです。彼らは改宗者でした。
黙示録の七つの教会 ヨセフ・シュラム師メッセージ ネティブヤ日本支部
もう一つの解釈、本当のユダヤ人であったとすれば「外見上のユダヤ人」ということになります。
スミルナの町には、その他の都市よりも多くのユダヤ人が住んでいたと言われています。そして、実際に彼らは「キリスト教会」を迫害していたようです。
私は、どちらも正解だと思っています(笑)
もしかすると「改宗者」が率先して迫害していたのかもしれないなとは思います。だいたい「改宗者」の方が激しかったりするものです。
いずれにせよ、イエス様はスミルナの教会をののしっている人々を「自称ユダヤ人」と認識されたということです。
「ののしる人々」は、外見上のユダヤ人であるとみなされたのかもしれません。
「自称ユダヤ人たち」が「キリストの教会」を憎んでいたことは、使徒の働きを読めば何となく理解できます。
スミルナの「自称ユダヤ人たち」も同じだったのだろうと想像できます。一説によると、彼らは、自分たちに危害が及ばないように「率先して迫害していた」と言われています。
自分たちと「キリスト者」とは違うグループだと、はっきりさせたいがために「ローマに従わない人々だ」と告発していたということです。そこには、もう少し複雑な事情があるようですが、あまり詳しい資料が手元にないので「こういう事情だ」と確定はできません。
ただ、スミルナの教会が激しく「ののしられていた」ことだけは確かです。
主は言われます。
「ユダヤ人だと自称しているが実はそうでない者たち、サタンの会衆である者たちから、ののしられていることを知っている」と。
「自称ユダヤ人たち」は「サタンの会衆である者たち」だとイエス様は言われるのです。
「サタン」とは、直訳すると「反対者」「敵」という意味です。
主は、スミルナの教会に「ののしる者は、わたしの反対者、敵の会衆だ」と言っておられるのです。「ののしる者」の背後には「反対者」「敵」がいるのです。
「自称ユダヤ人たち」は、何らかの理由で激しくスミルナの教会を憎みました。その「憎しみ」をサタンは利用しました。
主の敵である悪魔は「ユダヤ人」も「キリスト者」も憎んでいます。どちらも滅ぼしたいのです。そして、どちらをも「利用する」のです。私たちは「利用」されてはなりません。
幸いなのは「あざける者の座に着かない人」です。
「あざける人」「ののしる人」は、知らないうちに「サタンの会衆」とされているのです。彼らは利用されているのです。
本当の敵は「悪魔」なのです。彼の名は「サタン(反対者)」です。
「機会」とは「場所」とも訳せます。
悪魔は、私たちの中に「場所」を得ようと狙っています。私たちを「利用」する気なのです。決して「場所」を与えてはなりません。「機会」を与えてはなりません。
私たちが「ののしられた」とき、ののしった人を見るならば「怒り」が湧くでしょう。しかし「血肉」を見てはなりません。その背後に「敵」がいるのです。
反対されれば腹が立ちます。罵られれば傷つきます。
しかし、彼が「悪魔に捕らえられて思いのままにされている」ことを覚えてください。
もちろん、取り憑かれているとか、その人が「サタンの手先」だとか言っているのではありません。このことは、またいつか「霊的戦い」の学びができれば、その時に詳しくやりましょう。
今は、ただ「私たちの格闘は血肉ではない」ということを覚えていてください。スミルナの教会は「霊的戦い」の中にいました。この苦しみをもたらしたのは、明らかに悪魔です。
さて、この続きは次回に学びたいと思います。
愛する兄弟姉妹。
主が「知っている」と言われることを忘れないでください。
主は、すべてをご存知です。
あなたの苦難を知っておられます。貧しさも知っておられます。
「どうして、神様」という叫びも知っておられます。
理由が分からない悲しみや苦しみが、私たちの人生には起こります。その理由は、ずっと分からないかもしれません。もしかすると、時が来れば分かるのかもしれません。
ただ確実に言えることは「主が知っておられる」ということです。
イエス様は、スミルナの教会に「敵を滅ぼす」とは言われませんでした。
「苦難から救う」とも言われませんでした。
「貧しさから解放しよう」とも言われませんでした。
ただ「実際には富んでいる」と言われました。
そして、ただ「わたしは知っている」と言われたのです。
もし、あなたが苦しみ、悲しみの中にあるならば「実際の姿を教えてください」と求めてください。
主の御目に、今のあなたは「実際」どのように映っているのでしょう。
人は、あなたを「拒絶」しますか?
しかし、主はあなたを受け入れられます。あなたを抱き寄せ「愛する者よ」と言われます。
人は、あなたを「役に立たない」と言いますか?
主は、あなたを「高価で尊い」と言われるでしょう。
あなたは「貧しい」ですか?
いいえ、あなたは「富んで」います。
あなたは「倒れそう」ですか?
もし倒れたとしても滅びません。
私たちは「主にある実際の姿」を見るのです。見えない領域において「実際」どうであるかが大切なのです。
覚えてください。
「わたしは知っている」と言われる方が、常にともにおられることを。その苦難は知られています。その悲しみも知っておられます。あなたは、決して見放されてはいないのです。
あなたの「実際の姿」を常に見つめておられる方がともにおられます。その方は「世にあるあなたの苦しみ」をもご存知です。
主は、あなたに「空想の世界を生きよ」と言われているのではありません。
「世にある苦難は一時的なものだ」と言われるのです。そして、「あなたの実際は、世にある姿ではない」と言っておられるのです。
見えない領域があります。見えているものは「すべて」ではありません。
私たちは「初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方」の言われることに耳を傾けましょう。
人が味わうすべての苦しみを経験された方が「わたしは知っている」と言われるのです。
私たちは、その御言葉を心に刻んで歩くのです。
今日も、すべてをご存じの方がともにおられます。
祝福を祈ります。