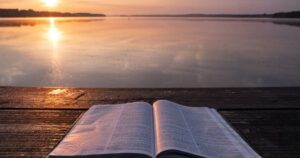黙示録2:6
しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。わたしもそれを憎んでいる。
わたしもそれを憎んでいると言われます
黙示録2章6節~7節を学びます。今度こそ本当に「エペソにある教会への手紙」についての学びは終わりです(笑)
さて、前回は「初めの愛から落ちてしまったエペソの教会の姿」を見ました。
イエス様は「悔い改めて初めの行いをしないなら、燭台を取り除く」と言われました。「初めの愛」から離れることは、主イエスから離れることです。いのちの君から離れてしまったならば、もはや「教会ではなくなる」のです。
イエス様は、かなり厳しい宣告をされました。しかし、エペソの教会には、まだ望みがありました。
「あなたにはこのことがある」とイエス様は言われます。
「初めの愛」からは離れてしまったけれど、まだ「このことがある」と言われます。
「エペソの教会よ、あなたは、わたしと同じものを憎んでいるね」と言われるのです。
エペソの教会は「主と同じもの」を憎んでいました。彼らはまだ「主と同じ心」を持っていたのです。
イエス様は「このこと」を誉めてくださったのです。
主が「ご自身と同じ思いを持つこと」を重視しておられることは明らかです。
主は「その心がご自分と全く一つ」となっている人々に御力を現わされます。
主は「同じ思いの人」と働きたいと望まれるのです。
エペソの人々はこの点において「部分的」ではありますが「主と同じ思い」をもっていました。そのことをイエス様は評価されています。
「初めの愛から離れた」と厳しく責められたけれど、彼らにはまだ「このこと」があるのです。
あなたはどうでしょう?
あなたは何を愛しているでしょう。
あなたは何を憎んでいるでしょう。
私たちは「その心が全く一つ」となっているでしょうか。
私たちは「部分的」ではなく「その心が全く一つ」とされるよう、切に、切に求めましょう。
異端の教えとは何でしょう?
イエス様は「わたしもそれを憎んでいる」と言われます。
主イエスが憎んでいると言われるのは「ニコライ派の行い」のことです。
ここで注意するべきことは、イエス様が憎んでおられるのは「ニコライ派の人々」ではなく「その行い」であるということです。
イエス様は「すべての人の贖いの代価」として十字架に架かってくださいました。御父は、ひとり子を与えるほどに「世」を愛されました。
私たちは誤解してはなりません。
確かに「教え」において妥協することはできません。妥協などしてはならないのです。
しかし「異なった教え」を告げ知らせる「人々」を憎んではなりません。彼らも「主が愛しておられる人々」だからです。
イエス様は「ニコライ派の行い」を憎まれました。
それは、どのような行いだったのでしょうか。
「ニコライ」とは「民を征服する」「民の勝利」という意味の名前です。確かに、ニコライ派の教えは「人々を征服」したように思います。
「ニコライ」という名前が表す通りに、彼らは「民を征服」しました。彼らの「教え」は多くの人を虜にしたのです。それは「魅力的」に見えたのでしょう。
彼らの「教え」をできるだけ簡単に説明すると「恵みの乱用」ということになるかと思います。
彼らは「恵みの御霊を侮る人々」でした。
彼らは「霊的」なことを語りましたが、誰よりも「肉的」な行いをしていました。
救われて聖なる者とされたのに、彼らは自ら「汚れ」に戻って行きました。しかし、彼らの「教え」によれば、それこそ「霊的」なことであったのです。
「異端の教え」は、教会の中の人によって「ひそかに持ち込まれ」ます。これは「外部」ではなく「内部」から起こります。偽教師は「あなたがたの中」に、つまり「私たちの中に」現れるのです。
その「教え」は「滅びをもたらすもの」です。ゆえに、イエス様は「異端の教え」を憎まれるのです。
「異端の教え」とは「自分たちを買い取ってくださった主を否定する教え」のことです。
イエス・キリストの十字架を空しくする「教え」はすべて異端であると私は思います。それは、人を滅びに導く教えです。
主は、ご自身の愛する者を「滅びに導く教え」を激しく憎まれると私は思います。
彼らは何を教えていたのでしょうか?
一説によると、彼らは「階層重視」であったと言われます。ニコライ派の「教え」について学ぶと、ほとんどの場合「不道徳」「汚れ」に注目されています。確かに、彼らは「かなりオカシイ人たち」です。
しかし、彼らの教えの最も「悪い部分」は「神と私」の間に「一枚噛ませたこと」だと私は思います。
彼らは、神と人間を切り離そうとしていました。「神のところへ直接行けるわけはない。見ろ。神は偉大すぎて、それに直接おまえと関わる暇などない。」と彼らは考え、階層制を設けました。「あなたは願い事をAという人に持って行きなさい。そうすれば、その人はまたBという人のところに持って行く。そのように梯子を登るようにして、最後は神の御座の前に行きつく」というものです。
黙示録の封印を解く チヤック・スミス著 プリズム社
聖書は言います。
誰をも、何をも「神と私」の間に入れるべきではありません。どんな人も「仲介者」にはなれません。私たちの仲介者は「人としてのキリスト・イエス」だけです。
マリアを「仲介者」とする教えには決して賛同できません。カトリックの人々を愛します。けれど、彼らの「教え」をすべて肯定することはできません。
これは、カトリックの人々だけの問題ではありません。「誰か一枚かんでいる」という状態が得てして教会にはあるように思います。
私の牧師は、私を救いに導いてくれたとき言いました。
「家に帰って、一人で神様にすべての罪を告白しなさい。具体的に言いなさい。でも誰かに聞いてもらわなくていいからね。」
そして、続けていいました。
「罪を紙に書きだしてね。終わったら、破いてポイポイ。これで終わりね」
私は、言われた通りにしました。誰にも「懺悔」しませんでした。ただ、神様の御前に告白しました。
そして今、私は「救われている」と確信しています。誰かの「太鼓判」は必要ありません。聖霊の「証印」で充分です。
神様とあなたの間に「誰か」を挟む必要などないのです。「仲介者」はすでにおられるのです。イエス様以外に私たちの「仲介者」は必要ありません。
邪魔する者とはつまずかせる者と同じです
「異端の教え」は、だいたいにおいて聖徒を「かしらであるキリスト」から引き離すものです。
愚かな人たちは「御使いを見た」という経験を誇りました。また、ある人は「どれだけ断食をしたか」を誇りました。
そして、おそらく彼らは言ったのです。
「君は、まだそんなことも経験していないのか」
「あの先生のところへ行ってごらん。君にもそれが分かるようになるから」
「もっと祈って断食すれば、きっとできるよ。私にもできたのだから」
それを聞いた真面目な聖徒は「自分もそうなりたい」と願うでしょう。そして、彼らのアドバイスを聞いて「そのとおり」にするでしょう。
「悪気」はなかったのかもしれません。彼らは本当に「御使いを見た」のかもしれません。彼らは「へりくだって」いるように見えたのかもしれません。しかし、彼らは間違っています。十字架の御業に「何か」を足すことも引くことも、けっして許されないのです。
私たちは注意せねばなりません。
教会の中に「霊的な劣等感」を抱かせる風潮があってはなりません。「神」に近づくために「人の側の行為」は不要なのです。主につながるために「御使いを見る」必要はないし「聖書を丸暗記」する必要もないのです。
「神と私」の間に「何かを噛ませて」来る人々には気をつけなさい。あなたに「霊的な劣等感」を抱かせる人々からは離れればよいのです。それらの人々が「霊的マウント」を取ってきても放っておきなさい。
私たちは「誰か」や「何か」につながってはなりません。私たちは「かしら」にしっかりと結びつけばよいのです。
この点において、私には反省すべきことが多々あります。「相談」や「カウンセリング」をする立場の人は特に注意が必要だと思います。
決して「神」と「その人」の間に入ってはなりません。その人が「私」の言うことを聞くようになってはならないのです。その人が「かしら」につながるように祈らなければならないのです。
まず「私」が「かしら」にしっかりと結びつくことです。
自分の「経験」や「体験」につながってはなりません。「知識」でさえも誇るべきものではありません。知っていなければならないほどのことも「知らない」のだということを覚えておかねばなりません。
私には誰かを「成長させる」ことはできません。
「育てられる」のは神です。神によって育てられ成長した人だけが「かしら」に結びつきます。
私は、決してそれを邪魔してはならないのです。
私は「わざわい」になりたくありません。
誰かを「支える」ことと、誰かを自分に引きつけることは違います。「私のようになりなさい」と私たちが言うとき、それは「かしらにつながる自分」のようになりなさいという意味でなければなりません。
「神」と「人」の間に入ってはなりません。
この御言葉に反する教えは「すべて間違い」であることを忘れてはなりません。
その実践は汚れていました
さて、ニコライ派の教えの実践は「不道徳」「汚れ」だと言われます。
パウロは「決してそんなことはありません」と言いました。けれど、ニコライ派の人々は「その通りだ」と言いました。
つまり、彼らは「恵みの下にあるのだから罪を犯そう」と言ったのです。
ニコライ派については、あまり多くの情報は残っていません。ですから、一般的にグノーシス主義と同じようなものと説明されることが多いようです。全く同じではなかったでしょうが、似たような「教え」であっただろうと思います。そして、同じように「汚れ」ていました。
初代教会の時代には、教会にはすでに「分派」がありました。コリント人への手紙を読めば分かります。そして、その「分派」から多くの異端が発生したであろうことは容易に想像できます。
ニコライ派について少し引用してみましょう。
アレクサンドリアのクレメンスの記録によれば、勝手気ままな放縦主義者たちだったようです。食べ物のことも、生活のことも、自由奔放で、どうであってもよいという立場のようです。もちろん、そのようにクリスチャンに教えるのです。偶像に献げたものであろうと自由に食べてよい、私たちの内的なたましいの救いには何の関係もないと教えるのです。
黙示録の7つの教会への手紙 柴田敏彦著 いのちのことば社
彼らは、私たちには考えられないような「不道徳」を平気で行っていたようです。
パウロはコリントの教会が「異邦人の間にもないほどの淫らな行い」をしていると言っています。
「コリント」という町は「不品行の代名詞」として用いられるほど「不品行で有名」な所でした。そのような「コリントの異邦人の間にもないほどの淫らな行い」が教会の内側で起こっていたということです。
このような「不品行」がエペソの町でも行われていたのでしょう。
これは「恵みの乱用」でした。「行いではなく恵みによって」という教えが、歪曲されたのです。恵みが悪用されたと言ってもいいでしょう。
たましいの救いを受けている私たちは、そんな周囲のことで、汚されたり滅ぼされたりすることはない。どうぞご自由にとたましいの救いを強調しました。~中略~
彼らはこのとんでもない教えを、もっともらしい最新の生き方として教えていたようです。
黙示録の7つの教会への手紙 柴田敏彦著 いのちのことば社
W・Eシューベルトという宣教師は「この偽教理と実践は、今日においても危険なものであることを、私たちは知らねばならない」と言っています。
おそらく、私たちは進んで「不品行を行おう」とは思わないでしょう。むしろ避けようとするはずです。
しかし「新しい教え」についてはどうでしょう?
「あなたは、まだ古い教えに凝り固まっているのですか。主は、常に新鮮な油を注がれるのです」などと言われたならどうですか?
初代教会の聖徒たちも「新しい教え」に魅力を感じたのです。「新しいぶどう酒」「新しい皮袋」と言われると、私たちは弱いのです。遅れをとってはならないぞと思ってしまうのです。イエス様も「新しい教え」を説かれたな、などと思ってしまうのです。
しかし、どうか覚えてください。
イエス様の教えは「新しく」聞こえますが、その「教え」こそ創世の初めから変わらない不変のものであるということを。
イエス様は「律法」を廃棄されたわけではありません。「律法」を成就されたのです。「律法」の目的、つまりゴールは「キリスト」です。イエス様は目的を果たされました。
イエス様は「新しい戒め」として「互いに愛し合う」ことを命じられました。私たちは、少なくとも二千年、同じ戒めを繰り返し読んでいます。もはや「新しく」ありません。
しかし、その戒めは「今日も新しい」のです。
「こは げに古き教えなれど 日々新しき歌とぞなる(聖歌525)」です。
自分だけが「真理を知っている」という人には気をつけなさい。
自分だけが「聖書を理解している」という人にも注意しなさい。
何でもかんでも「否定」する人の意見は確認しなさい。
何でもかんでも「肯定」する人の意見も確認しなさい。
私たちは「新しい解釈をしています」という団体からは逃げなさい(笑)
私たちは、みなが「天の御国の学者」とされましょう。
心の倉に「新しいもの」も「古いもの」も、主が与えてくださるものを蓄えます。そして、必要な時に、必要なものを引っ張り出してもらえるように整えられましょう。
決して離れてはなりません
惑わされないように。終わりの日には、ますます惑わしが強く、そして巧妙になります。
誰かの後を追いかけるのではなく、イエス様に「根付く」のです。
教えの風に吹き回されるのではなく、自分の神を知って「堅く立つ」のです。
ニコライ派であろうと「最新の教え」であろうと、そのようなものに振り回されてはなりません。しっかりと「みことば」を自分で掴むのです。
求めるのは「物」や「事」ではありません。私たちは「かしら」であるキリストに、しっかりと結びつくことを求めるのです。そうすれば、おのずと、他の器官とも連携をとることができるでしょう。
「耳のある者は、御霊が諸教会に告げることを聞きなさい」とイエス様が言われます。
私たちは聞きます。私たちは御霊の告げることを聞きたいと願います。
私は「イエスを神の御子と信じて」います。あなたはどうですか。
「イエスを神の御子と信じる者」であるならば、その人は「勝利を得る者」です。
その人は「いのちの木から食べること」が許されます。
私たちは「いのちの木」である方のもとに行きましょう。主が招いておられます。
「初めの愛」から決して離れてはなりません。イエス様が開いてくださった至聖所への道を、自ら閉ざしてはなりません。
私たちは「恵みの下」にいます。ゆえに「聖なる者」として歩みます。
イエス様は祭司として、燭台の間を歩いておられます。
それは「ともしび」を整えるためにです。祭司には「ともしび」を絶やさないようにする役目があるのです。
「ともしび」は絶やしてはなりませんでした。祭司は、毎朝、毎晩、それを整えるのです。純粋なオリーブ油が注がれました。聖所は常に照らされ続けていました。
教会は「燭台」です。それは常に「ともされている」必要があります。イエス様は、燭台の間を歩かれます。油を注いで回り、ともしびを調整してくださいます。
私たちは、常にイエス様の手の中で整えられています。何も恐れる必要はないのです。
しかし、もし「初めの愛」から落ちたまま、気がつかず、悔い改めないままであるならば…
「燭台は取り除かれる」でしょう。おそらく、それは気がつかない間に起こります。
エペソの教会から学んだことを忘れないようにしましょう。
「初めの愛」から決して落ちてはなりません。
祝福を祈ります。