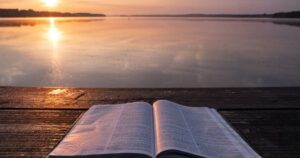黙示録1:3
この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たちは、幸いである時が近づいているからである。
ヨハネは自分の見たすべてのことを証した
使徒ヨハネは「自分が見たすべてのことを証しした」と言っています。
黙示録とは全体として「預言の書」です。
「すぐに起こるべきこと」が記された書です。
しかし、それと同時に「ヨハネの証」が記された書でもあります。
イエス様はヨハネに言われました。
一般的には、このイエス様のご命令は「黙示録のみ」に当てはめて考えられます。
つまり「あなたが見たこと」とは、黙示録1章の主イエスの幻のこと。
「今あること」とは、黙示録2章から3章の七つの教会への手紙のこと。
そして「この後起ころうとしていること」とは、黙示録4章以降の出来事のこととします。
その解釈に異論はありません。ただ、別の解釈もあります。
ヨハネは五つの書を書きました。「ヨハネの福音書」「ヨハネ第一の手紙」「ヨハネ第二の手紙」「ヨハネ第三の手紙」、そしてこの「ヨハネの黙示録」の計五つです。
そして「ヨハネの福音書」(過去)、「ヨハネの第一、第二、第三の手紙」(現在)、そして「ヨハネの黙示録」は全体として「この後起こること」になり、全体として預言書になります。
世の終わりが来る「ヨハネの黙示録」私訳と講解 奧山実著 マルコーシュ・パブリケーション
個人的には、この解釈の方が腑に落ちます。
「あなたが見たこと」とは「ヨハネの福音書」のこと。
「今あること」とは「ヨハネの手紙」のこと。
そして「この後起ころうとしていること」とは「ヨハネの黙示録」のこと。
そうであれば「ヨハネの黙示録」が「ヨハネの証」であることが理解できます。
ヨハネは一貫して「神のことば」である方を証しているのです。
「福音書」において「神のことば」である方が何をされたのかを証しました。
「ヨハネの手紙」において「いのちのことば」である方が、今、何をしておられるのかを証しました。
そして「黙示録」において「血に染まった衣をまとう神のことば」と呼ばれる方を証しているのです。
私たちは「神のことば」「いのちのことば」と呼ばれる方に目を留めます。
黙示録を学ぶことによって「ヨハネの見たすべてのこと」を私たちも見るのです。
黙示録が使徒ヨハネに告げられた理由がここにあります。
黙示録には「神のことばとキリストの証」が記されています。
主イエスの教え
十字架の死、葬り、よみがえり
今、主が天で行われていること
主が後に備えておられること
主の恵み、聖さ、そして権威
「神のことば」がそれを示します。それは「イエス・キリストの証」です。
ヨハネは預言者です。黙示録は預言の書です。
ヨハネは証人です。黙示録は証の書です。
ヨハネが見た「神のことば」を私たちも見るのです。
自分のイメージ通りの方を見つけることができなくても「うろたえて」はなりません。思ったような方がおられなくても「目をそむけて」はなりません。
記されていることは理解できなくても「そのまま」受け留めるのです。
「ヨハネの福音書」が真実であると私たちは信じています。
そうであるならば、同じ使徒ヨハネが記した「黙示録」もまた信頼に足るものであると信じることができるでしょう。
七つの至福のことばの一つ目です
黙示録には「幸いである」と言われる聖句が七つあります。
「七つの至福のことば」などと呼ばれます。この箇所は、その一つ目です。
「幸いである」とは「うらやましがられる状態にある」という意味です。「幸福な」「至福の」などと訳せます。
黙示録の最初に「幸いな状態」について語られるのには意味があると思います。
これは、私たちが黙示録を学ぶときの「心得」であると受け取るべきでしょう。
幸いなのは「どのような人たち」でしょう?
幸いなのは「この預言のことばを朗読する者と、それを聞いて、そこに書かれていることを守る者たち」です。
この人たちは「セット」です。
ここで「朗読する者」は単数形で「それを聞いいて守る者たち」は複数形の語が使われています。
「黙示録」は「手紙」ですから「受け取り人」が存在します。
それが「七つの教会」の聖徒たちです。
この御言葉から分かることは「受け取った人々」は、手紙を回し読みにしたのではなく「公の場で朗読されるものを全員で聞いた」ということです。
そして「幸い」なのは「朗読する人と聞いて守る人たち」なのです。つまり、その集会に集って「手紙」を神のことばとして受け取ったすべての聖徒が幸いなのです。
聖書を朗読することは最も良いことの一つです
パウロは若いテモテに勧めて言いました。
とにかく「聖書朗読と教えと勧めに専念せよ」と言うことです。
ユダヤ人たちは会堂で「聖書を朗読」していました。
イエス様も会堂で「イザヤ書を朗読された」とルカが言っています。
初期の聖徒たちも集まって「聖書朗読」をしていたようです。その集会では「使徒たちの手紙」も朗読されたようです。
ところが朗読されても意味の分からない人がいたので、それを分かりやすく解説したのです。それが説教です。難しいので「分かりやすく」説いてやったのですから、説教の絶対条件は「分かりやすい」ということなのです。だから説教よりも重要なのが「聖書朗読」であるということが分かりますね。神の言、そのものなのですから。
世の終わりが来る「ヨハネの黙示録」私訳と講解 奧山実著 マルコーシュ・パブリケーション
「説教」よりも「聖書朗読」のほうが重要だという意見に、私は激しく同意します。
教会の礼拝は「説教中心」です。最も大切なのは「説教」であると多くの人が思っています。
しかし、本当に重要なのは「神のみことば」なのです。
私は、すべての聖徒が「牧師」になればよいのにと思っています(笑)
もちろん、与えられた賜物があります。みなが牧師ではありません。
けれど、皆が「弟子」ではあるべきです。
そして、皆が「弟子をつくる」ことはできるでしょう。
「私は説教なんて、とてもできません」
「知らない人に伝道するのも苦手です」
多くの人がそのように言うのを聞いてきました。
「あなたみたいに口から生まれた人には分からないでしょうがね、献身を勧められるのは苦痛なんですよ」と怒られたこともあります(笑)
けれど、あえて言いますが、それは誤解です。私は口から生まれていません。そのように見えるのでしょうが、正直、語るのは苦手です。でも「語れ」と言われれば語ります。「歌え」と言われれば歌いますし「踊れ」と言われれば踊ります(笑)
しかし、なぜ「献身」イコール「語らなければならない」と思っているのでしょう?
みなが「牧師」ではないし、みなが「伝道者」でもないと書いてあるではないですか。
「語る賜物」がなければ「献身」できないなんて聖書のどこに書いてあるのでしょう?
「説教中心」の礼拝が誤解を招いているならば、それは改善されなければならないかもしれません。
聖徒はみな「聖なる生きた献げもの」です。教会で奉仕していなくても、すべての聖徒は「献身者」です。
もし、語れないけれど「何かしたい」と本気で願っているならば「聖書朗読」を始めてはどうでしょう。
少し私の証にお付き合いください。
まずは、ある説教者の話から。
その先生は「ヤコブ書」を丸々暗記していたそうです。
そして、自分の「説教」かのように感情を込め「ヤコブ書」を語り始めたそうです。
「兄弟たち、様々な試練に会うときは、それをこの上ない喜びと思いなさい」
そのような調子で1章から5章までを聖書を見ずに朗読したのです。
その日、会堂に集まった人々は感動の渦に包まれました。それは暗記力の素晴らしさに感動したからではありません。そこには、確かに御霊の臨在があったのです。多くの人が「みことば」に心を刺され悔い改めの涙を流したと言います。
実は、私もこれと全く同じことを経験したことがあります。
それは、ある若い姉妹の証の時でした。
その姉妹は「主のために5年間」を献げると約束して、18歳ぐらいの時に台湾から日本に来たのです。
その最終日、今までのことを証する場が設けられました。
その姉妹が、説教壇に立ったとき、みなは「5年間の感謝の証」を聞こうと待ち構えていました。
しかし、彼女は「ヤコブ書」を朗読し始めたのです。
彼女は「語るように」読み始めました。
最初、私は何が起こっているのか分かりませんでした。
「いつまで読み続けるのだろう」とちょっと思っていたことは認めます(笑)
彼女は、最後まで読み切りました。
そして、続けて信じられないことを言ったのです。
「もう一度、今度はゆっくりと読みますね」
あの衝撃は忘れることができません。「今度はゆっくり」と宣言した通り、彼女は1回目よりも「ゆっくり」と読み始めたのです。
さて、ここで不思議なことが起こりました。
「ゆっくり」読まれる「ヤコブ書」のことばが、私のうちを「温め」始めたのです。
説明はできません。ただ心が「熱く」なって、そして、知らないうちに私は泣いていたのです。
それは「号泣」に近い泣き方でした。
ちなみに、私は「説教」を聞いて泣いたことは「ほとんど」ありません。感動はしますが泣きません。30年間で号泣したのは「3回」ぐらいです。
彼女は一言も「自分の経験」を語りませんでした。しかし、私には、彼女が経験したことが「ヤコブ書」であったことが、なぜか分かりました。
そして、その場に聖霊様がおられることが、とてもよく分かりました。「みことば」が生きていたのです。
周りを見る余裕はなかったけれど、後で聞いたところよれば、集った人たちのほとんどが泣いていたそうです。
私が今まで聞いた「講壇からの話」で最も感動したのは、所謂「説教」ではなく「聖書朗読」であったということです。
私は「みことばの力」を信じています。それは、体験からも確信しているのです。
「上手く語ることができない」「教えるのは苦手」であっても問題ないと強く言える理由がお分かりいただけたでしょうか。
私は、日本中に「聖書を読む会」ができればよいと願っています。二人でも三人でも「聖書朗読」はできます。
日本中が「神のことば」で満ち溢れることを願います。
とくに「黙示録」を朗読することを勧めます。
意味を理解することができなくても「朗読すること」「聞いて心に留めること」はできます。
そのようにする人たちは「幸いである」とわざわざ記されているのです。
私たちは「黙示録」を読みましょう。
皆で集まって読みましょう。
もちろん、一人で静まって読むことも良しです。
とにかく、主が約束された「幸いである」という状態を体感するまで「黙示録」を読み続けていきましょう。
そこに書かれていることを守ること
聖書では「聞く」とは「従う」ことと同じです。つまり「聴従」です。
「聞く」ならば「従う」それが当然なのです。
「聞いて」も「従わない」ならば、それは「聞かなかった」と同じでしょう。
ここで「守る」と訳されている言葉を使徒ヨハネは他の書簡でもよく使用しています。
神の命令を「守る」ことは重荷にはならないと使徒ヨハネは言います。
黙示録を朗読し、それを聞いて、そこに書かれていることを「守れ」と言われると「重荷」を感じてしまうでしょう。
何か恐ろしいことが起こるけれど歯を食いしばって耐え忍ばねばと思います。
耐え忍ぶために「すさまじい覚悟」が必要なのだと考えてしまうのです。
しかし、ヨハネは言います。
「神の命令は重荷にはなりません」
「重荷」と感じるならば、それは「愛していない」からなのです。
覚えてください。
確かに「命令」はあります。「重荷」は負わなければならないでしょう。最後まで「耐え忍ぶ」必要があることも事実です。
しかし、私たちは常に「戒め」ではなく「イエス・キリスト」に目を留めるのです。
「重荷」に押しつぶされるように感じるなら祈ります。
しかし、「主よ、重荷を負えるようにしてください」と祈ってはなりません。
それは、あなたには「無理」だからです。
「重荷」に押しつぶされそうならば、こう祈るのです。
「主よ、愛を増してください。あなたを慕い求める心をお与えください」
イエス様への愛が満ちれば、それは重荷にはなりません。
自主的なしもべとして
神を愛する者は「神の命令を守る者」です。
「神の命令を守る者」が「神を愛する者」だからです。
そこには「自主性」があるのです。
ヨハネは「イエスの愛された弟子」ですが「しもべヨハネ」でもあります。
パウロは「奥義を委ねられた者」ですが「キリスト・イエスのしもべ」と名乗ります。
彼らは「自主的にしもべとなった」のです。
七年目には、奴隷は自由の身になれるのです。
しかし「主人を愛する奴隷」が「明言する」なら、彼は一生、その主人に仕えることができるのです。
ヨハネやパウロが、自分を「キリスト・イエスのしもべ」と呼ぶときには、この「主人を愛する」と明言した奴隷のことを言っているのです。
主人は「愛する」と明言した奴隷の「耳をきりで刺し通し」ます。
「奴隷」は、一生、主人に仕えるために「耳」を差し出すのです。
イエス様ご自身も、御父に「耳」を差し出してくださいました。
御父を愛し、神の家族である私たちを愛するがため「仕える者の姿」をとってくださいました。
イエス様は御父に従われました。十字架の死にまで従われました。
それは「仕方なく」「しぶしぶ」ではなく「御父と私たちへの愛」ゆえに従われたのです。
愛する兄弟姉妹。
主の愛は明らかにされました。
私たちは、どうでしょう?
あなたは、主を愛すると「明言」しますか?
愛するならば「耳」を差し出しましょう。
私たちは、少年サムエルのように、呼ばれたなら答えるのです。
「はい。お話しください。しもべは聞いております」
主は、私たちの「耳」を呼び覚まして下さいます。私たちの「耳」を開いて下さいます。
私たちは、主を愛しますと「明言」したしもべです。
私たちは「耳」を差し出したしもべです。
語られたならば「聞き従い」ます。
しもべの「耳」で聞く者は幸いです。
黙示録は「しもべたち」に示されたものです。
私たちは「主と兄弟姉妹を愛しています」と明言するしもべの心を持って「黙示録」を学びましょう。
祝福を祈ります。