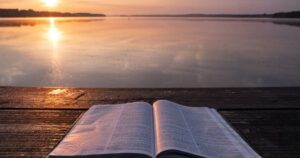黙示録3:14
また、ラオディキアにある教会の御使いに書き送れ。「アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方がこう言われるー。
アーメンである方、確かで真実な証人、創造の源である方から
さて、とうとう七つ目の教会の学びに入ります。
イエス様は「アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方」として、ご自身を啓示されました。
一つ一つ見て行きましょう。まず、一つ目は「アーメンである方」です。
イエス様は大切なことを言われる時に「まことに、まことにあなたがたに告げます」と言われました。
この「まことに」が「アーメン」です。その他「しかり」と訳されることもあります。
「アーメン」という語は、なかなか説明するのが難しいことばです。
アーメンという言葉は、どういう言葉でしょうか。ヘブライ語では、この単語は非常に独特な言葉です。この単語は、3つの文字でできていますが、それはヘブライ語のアルファベットで言うと、最初の文字アレフと真ん中の文字メムと、最後の文字タヴです。これはエメット(真理)という意味でもあり、すべてのものを含むという意味があります。初めであり、終りであり、すべてのものの中におられる方を指しているのです。
黙示録の七つの教会 ヨセフ・シュラム著 ネティブヤ日本支部
説明を聞いても意味を把握するのが少し難しいですね。
これは、個人的な解釈ですが…
つまり「アーメンである方」というのは、出エジプトの時にモーセに現わされた「神の御名」と同じような意味なのではないかと思います。
イエス様は、モーセに啓示された「わたしはある」と言われる方です。
この方は、すべての人にとっての「存在意義」であり、すべての「意味」です。
初めであり終わりであり、その中にある「すべて」でもあられます。
イエス様こそ「御父への唯一の道」です。そして、神の「真理」の具現であり、永遠で豊かな「いのち」そのものです。
ラオディキアの教会は「アーメンである方」を知らなければなりません。
二つ目の啓示は「確かで真実な証人」です。
「確かで」とは「信頼できる」「忠実な」という意味です。
イエス様の証言は常に「真実」です。この方が言われることは「信頼できる」のです。
御父にとっても「確かな証人」であり、私たち聖徒にとっても「信頼できる証人」であられます。
三つ目の啓示を見ましょう。
イエス様は「神による創造の源である方」です。
イエス様は「見えるものも見えないものも」造られた方です。
イエス様は「見えるもの」の源であると同時に「見えないもの」の源でもあられます。
ですから、私たちは「見えないもの」が枯渇したときにも、この方のもとへ走るのです。
「喜び」が枯渇したならば「生ける水の川」の源である方のもとに行けばよいのです。
「アーメンである方、確かで真実な証人、神による創造の源である方」とは、七つの教会への手紙の中で「最も大いなる啓示」であるように思えます。もしかすると、他の教会への啓示を「すべて含む」お姿なのかもしれません。
このような偉大な啓示が与えられた「ラオディキアの教会」とは、どのような教会なのでしょう。
彼らには「称賛のことば」はありません。「非難」と「忠告」そして「主の思い」が記されています。
今回は「非難」されている部分について学んでいきます。
あなたは生ぬるいと言われます
イエス様は、ラオディキアの教会に対して「あなたは冷たくもなく、熱くもない」と言われました。
そして、続けて「むしろ、冷たいか熱いかであってほしい」とも言われました。
ラオディキアの町には、今でも「水道管」の遺跡が残っています。この町は、他の町から「水」を引いていたのです。
ラオディキアは「コロサイ」と「ヒエラポリス」の間に位置します。
「コロサイ」からは、雪解けの「冷たい水」を引いていました。
「ヒエラポリス」は温泉で有名な町です。沸騰するほどの熱い温泉が湧いていたそうです。ラオディキアの人々は、その温泉の「熱い水」を自分たちの町に引いていました。
「冷たい水」は雪解け水です。冷たいものを飲むなら「スッキリ」します。リフレッシュします。生き返るような気持ちがするでしょう。
「熱い水」は温泉です。日本以外の国では、たいてい「温泉」とは飲むものです。もちろん、ラオディキアの人々も「癒し」を期待して飲んだのだと思います。
「なまぬるく」:近くの双子都市ヒエラポリスの「熱い」健康水、また「冷たい」コロサイの水との比較。ヒエラポリスから水路でラオデキヤに届いた水はなまぬるかった。ラオデキヤの教会は霊的に病んでいる者に対する癒しも、霊的に弱っている者への元気づけもできなかった。
ひとりで学べるキリストの啓示 K・フルダ・伊藤著 文芸社
「なまぬるい」とは、どういうことかラオディキアの聖徒には、よく分かったのだと思います。
沸騰するほど熱い水も、キンキンに冷えた冷たい水も、ラオディキアの町にたどり着くころには「なまぬるく」なっていたと言われます。
「なまぬるい水」が、とても飲みにくいものであることをラオディキアの人々はよく知っていたのです。
イエス様はラオディキアの教会を「なまぬるい」と言われました。
彼らの「行い」が「なまぬるい」と言われたのです。彼らは「世の光」でも「地の塩」でもありませんでした。イエス様を「否定」はしませんが、イエス様だけを慕うということもありません。
イエス様は、ラオディキアの教会に対して「嫌悪感」を抱かれたということです。
「冷たい水」でも「熱い水」でもない、こんな「なまぬるい水」飲めたものではない、吐き出してしまおうと言われたのです。
主は「なまぬるい」ことを「不快」に思われるのです。
「吐き出す」とは、直訳すると「嘔吐する」です。つまり、イエス様は「吐き気」を感じるほど「なまぬるい」ものがお嫌いだということです。
当然のことながら、ラオディキアの教会は自分たちのことを「なまぬるい」などとは思っていなかったでしょう。
恐らく自分たちこそ「中庸を行く正統的な教会である」と思っていたことでしょう。
これは、現在の私たち「キリスト教会」の姿を現しているとしか思えません。
ラオデキヤの教会の「冷たくもなく、熱くもない」「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」などという姿は、まさに再臨前の背教の教会の姿を現しているのではないでしょうか。
世の終わりが来る 奧山 実著 マルコーシュ・パブリケーション
ラオデキヤの教会は、フィラデルフィアと同じ「再臨前の教会」であると言われます。
フィラデルフィアは「携挙される教会」と言われ、ラオディキアは「残される教会」などとも言われます。
終わりの時代、私たちは問われます。
「わずかばかりの力」であっても「主のことばを守り、主の御名を否まない者」となるか、「なまぬるくて吐き出される者」となるのか、私たちは「決断」せねばなりません。
実はみじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸である
ラオディキアの教会は「ほどほどの教会」です。自分たちは「結構、うまくやっている」と思っています。
ラオディキアは、スミルナのように貧しい教会ではありません。貧しいどころか、彼らは「裕福な教会」です。
エペソの教会のように「偽使徒」を試す必要もありません。ラオディキアは「戦わない教会」です。波風など立たない「穏やかさ」が売りなのです。
彼らは「何もかも持っている教会」でした。不足はありません。自分たちで何でもできます。誰かに頼る必要はありません。自分たちの必要は「自分たちで」何とかできます。
学校が必要なら「自分たちで」造ることができます。教会員が安心して暮らせるように施設だって造れます。快適に礼拝に集えるように「会堂を整える」こともできます。
それのどこが悪いのでしょう?
多くの人が集まって、献げられた献金を「教会」のために用いて何が悪いのでしょう?
学びだってしています。聖書を学ぶことは「賢く」なることです。情緒も豊かになります。慰められます。励まされます。祈り会にだって出席しています。祈ると心が落ち着きます。
ラオディキアの教会の人々は「自分たちに悪いところなどない」と思っていました。
イエス様は、ラオディキアの教会に言われました。
彼らは、自分の本当の姿を知りませんでした。
今、目に見えている「私の姿」は、見えない世界における「本当の姿」とは別なのです。
イエス様がご覧になっているラオデキヤ教会の本当の姿は「みじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸」でした。
スミルナの教会とは「真反対」の姿です。イエス様はスミルナの教会にはこう言われました。
貧しくて、明日の食べ物にも困るような聖徒たちに向かって、主は「あなたがたは実際には富んでいる」と言われます。
なぜなら、スミルナの聖徒にとって「生きることはキリスト」であるからです。
イエス様は彼らにとって「人生そのもの」「生きていることのすべての意味」だったからです。
「お金持ち教会」であるラオディキアの何が「みじめ」なのでしょう?
「足りないものはなにもない」と言えるラオディキアのどこが「貧しい」のでしょう?
ラオディキアの教会は、知らない間に、イエス様を閉め出してしまっていたのです。
主は、ラオディキアの教会の中にはおられません。主は「戸の外に」立っておられます。
「自分は富んでいる」「豊かになった」「乏しいことはなにもない」とラオディキアの聖徒たちは言っていました。「自分たちだけで何でもできる」と彼らは言っていました。
つまり、そこに「キリスト」のおられる場所はないということです。
「祈る必要のない奉仕」は「神からの行い」ではありません。
私たちは「主よ、今日も無事に過ごせますように」などという形式的な祈りはします。
「主よ、あなたがいなければ一歩たりとも進めません」とすがりつくのは「困ったことがあった時だけ」ではないでしょうか。
貧しいスミルナの教会は、ただ「主だけ」を頼りに必死で生きていました。
モーセは、荒野の旅において主に嘆願しました。
モーセは「主の臨在」がともに行かないのなら、旅を続けることはできないと言ったのです。
私たちにも、このモーセの祈りが必要です。それも、毎日、必要です。
「主よ、今日、あなたの臨在がともにないのなら、私は何もすることができません。主よ、どうかともにおいでください」
私たちは、主がともにおられなければ「何もできない」ことを心に留めておくべきです。
イエス様を「閉め出した」なら、目に見えるところが「どのような姿」であっても、実際には「みじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸」なのです。
生ぬるく生きるのは「もったいない」のです
ラオディキアの教会が「みじめで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸」であるのは、イエス様を閉め出してしまったからです。
これは、本当に注意深く心に留める必要があります。
「キリストの教会」と呼ばれていても「キリストがいない」ということがあるということです。とても恐ろしいですね。
本当に、主イエスを外に追い出している教会などあるのでしょうか。それがあるのです。私は、まさにそのような教会にいましたから、よく分かります。教会といっても、この世のクラブと何も変わらないような所でした。
世の終わりが来る 奧山 実著 マルコーシュ・パブリケーション
私たちの「集まり」は「この世のクラブ」と同じであってはなりません。
一緒に食事をしたり、笑い合ったりするのがダメだと言っているのではありません。
私たちと「この世のクラブ」を区別するのは何でしょう。
モーセが「神の臨在」がともに行くように求めたのは「地上のすべての民」と区別されるためでした。
私たちの集まりと「世の集まり」の大きな違いは「神の臨在」です。
そこに「神の臨在」がともになければ、私たちの集まりは「世のクラブ」と同じです。
そして、そこに「神の臨在」を招きたいのなら「なまぬるさ」から脱却しなければなりません。
「中庸である」とは便利な言葉です。私は、救われたころ「真理は常に真ん中にある」と教えられました。教えてくださった先生を尊敬していますが、それは違うのではないかと、今は思っています。
神学生であったころ、ある先生が言いにくそうに教えてくれたことがあります。
「こんなことを言ったら危険人物だと思われるかもしれないけれど、真理は異端スレスレにあるのではないかと思う」と。
「異端スレスレ」という言葉の是非はともかく、確かに「真理はいつも中庸である」とは言えないと私も思います。
ある人は「異言」という単語を聞いただけで拒否反応を示すでしょう。
奇跡や病のいやしは「聖書の中だけのこと」と思っている人もいるでしょう。
「いや、確かに今の時代でも奇跡は起こるだろうけれど、滅多には起こらない」と思っている人もいるかもしれません。
あまり大きな声では言えないけれど、私は「全員が献身者になればいい」と思っています。しかも、本業を「献身」にして欲しいと願っています。今の仕事を辞めよ、とは言いません。
しかし、会社の中で大声で「イエス様を信じれば救われます」と叫んで欲しいと思います。手を置いて、職場で癒しを行う勇士になって欲しいと思います。まあ、そこまでは出来なくても、常に「この人が救われますように」と祈り心をもって働いて欲しいと願います。
どんな職業についていたとしても「本業は神のしもべである」と自覚して欲しいと願っています。
そして、みなが「羊飼い」になればよいと本気で思っています。みなが「開拓伝道」すればよいのにと心から思っています。みなが「とりなし手」になればよいのにと思います。
みなが「御霊の賜物」をこれでもかと用いて、初代教会のような御業が各地で起こればいいのにと思います。みなが異言を語り、預言をすればいいのにと思います。
北海道から沖縄まで「祈りの勇士」が与えられ、毎日、祈りと賛美で日本中を覆いたいと本気で願っています。みなが「自分の家」を教会にして「家の教会」が全国各地にできるように真剣に祈っています。
そんなことは「無理だ」と自分でも時々くじけますが、それでも祈り続けています。
「そこまでしなくても」と誰かに言われても、それでも従いたいと願っています。「行き過ぎだ」と言われることを恐れて、中庸を装ってきたことを後悔しています。
愛する兄弟姉妹。
私たちの人生は思ったより「短い」のです。
ですから「なまぬるく」生きるのは、あまりにも「もったいない」のです。
「豊かになった、足りないものは何もない」ことで満足ですか?
あなたが満足でも、主は満足だとは思っておられないでしょう。
私たちは「主に大いなること」を求めて生きましょう。
初代教会の人々が祈った祈りを、今、私たちも祈りましょう。
主が「みことばを大胆に語らせてください」ますように。
主が「イエスの名によって、癒やしとしるしと不思議を行わせてください」ますように。
日々、主の臨在がともにありますように。
「主の臨在」がなければ「この世の人」と区別されることはできません。
「なまぬるい生き方」とは、主の臨在を意識しない生き方です。
「世の中」がどうであるのか、「あの人」は何と言うだろうかと「世の中を意識」して生きるなら「なまぬるく」なります。
主の豊かな生ける水は、あなたを癒す温泉になります。また、あなたを潤しリフレッシュさせる雪解け水にもなるでしょう。
「なまぬるい者」から脱却しましょう。
聖霊が臨まれたなら「力」を受けるのです。それは「ダイナマイト」のような激しい力です。
それは、人目を恐れて「戸に鍵をかけて隠れていた弟子たち」を大胆にした力です。
ビクビクして「イエス様を否んだペテロ」を3000人以上の人の前で大胆に語らせた力です。
私たちにも、同じ聖霊様が注がれています。生ける水の川は、今日も、あふれています。
私たちは、もっと大胆に生きましょう。
自分を生き方を正直に見つめ直しましょう。
あなたは「なまぬるく」なってはいませんか。
あなたを「なまぬるく」させている原因は何でしょう。
「あなたのご臨在がともに行かないのなら、私をここから導き上らないでください」
主の臨在を見失えば、私たちの生き方は必ず「なまぬるく」なるのです。
主の臨在を求めましょう。誰かではなく、何かでもなく、ただイエス様だけを求めて生きるものとされましょう。
祝福を祈ります。