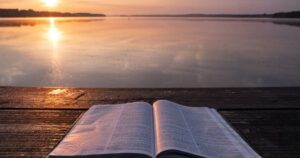黙示録3:7
また、フィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。「聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと、だれも閉じることがなく、彼が閉じると、だれも開くことがない。その方がこう言われる。
これは、小さな群れの確信を支える啓示です
「フィラデルフィアの教会への手紙」について学んでいきます。この手紙は「六番目の手紙」です。
イエス様は、フィラデルフィアの教会に「聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方」としてご自身を啓示されました。
黙示録1章の幻には啓示されていなかったお姿です。お姿というよりも、ご性質と言った方がよいかもしれませんね。
「少しばかりの力」とは、別訳では「少ししか力がなかったが」です。
しかし、同時に彼らは「わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかった」と称賛されています。
つまり、彼らは「信仰の力」は持っていたわけです。ですから、この「少ししかない力」とは、おそらく「小さな教会」で「影響力」がなかったという意味だろうと解釈できます。
八節後半での「あなたには少しばかりの力があって」と語るのを聞きますと、フィラデルフィアの教会を小さな群れであったと見てよいでしょう。
黙示録の7つの教会への手紙 柴田敏彦著 いのちのことば社
フィラデルフィアの教会は、確かに「小さな群れ」だったのでしょう。
エペソの教会やサルディスの教会のように「評判のよい教会」ではなかったのだろうと思います。
エペソの教会には「労苦と忍耐」がありました。「偽使徒の偽りを見抜き」ました。しかし、「はじめの愛から落ちた」と非難されています。
サルディスの教会は「生きているとされて」いました。彼らは「生きていると定評のある教会」でした。しかし「実は死んでいる」と非難されています。
フィラデルフィアの教会は「少しばかりの力」しかない教会でした。しかし、この教会には「叱責・非難」がありません。スミルナの教会と同じですね。
周囲の人々には「特に秀でたところのない教会」と思われていたのかもしれません。
しかし、イエス様は「わたしはあなたの行いを知っている」と彼らに言われます。
彼らの「行い」が具体的に何であるかはわかりません。もしかすると何か「具体的なこと」はなかったのかもしれません。
ただ彼らは「主のことばを守り、主の御名を否まなかった」教会でした。
フィラデルフィアの教会への手紙を読むと、イエス様が何を「重要視」しておられるのかが分かります。
イエス様は「少しばかりの力」を恥だとは思われません。私たちに「力がない」ことを責められることはありません。
主は、あなたは「わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかったか」と問われるのです。
フィラデルフィアの教会は、この点において称賛されたのです。
この「小さな群れ」は、その持てる力のすべてを「主のことばを守り、主の御名を否まない」ことに注ぎました。
そして、この「小さな群れ」に、イエス様はご自身がどのような方であるのかを知らせてくださったのです。
主は「聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方」としてご自身を啓示されました。
ここに「聖なる方」がおられます。
ここに「真実な方」がおられます。
そして、この方こそ「ダビデの鍵を持っておられる方」なのです。
これは、忠実なフィラデルフィアの聖徒たちの確信を深める啓示でした。
ダビデの鍵を持っている方
イエス様は「ダビデの鍵を持っている」と言われました。
私にはこの御言葉の意味がよく分かりませんでした。
私は、最初「ダビデの鍵」とは「ダビデの持っていた鍵」のことだと思ったのです。
そうであるならば「開かれた門」とは「天の御国の門」であって、そこに至る「鍵」とは「礼拝」のことだろうと考えたのです。
しかし、それでは文章の辻褄があいません。
イエス様は「ダビデの鍵を持っている」と言われたのです。「ダビデの持っていた鍵」ではありません。
次に考えたのが「ヒルキヤの子エルヤキム」に与えられた鍵のことです。
「エルヤキム」は、宮内長官に任命され「権威」を与えられた人です。彼に「権威」が委ねられ「ダビデの家の鍵」が置かれたとイザヤは記しています。
この「エルヤキム」という人は、明らかに主イエスの型です。
七世紀のヒゼキヤ王の時代、財務長官シェブナが降職させられた後、エルヤキムがその職に昇進させられたとき、エルヤキムには完全な管理権「ダビデの家の鍵」の所有が約束された。エルヤキムが肩に背負った輪型のつり鎖に掛けた重い鍵は、王との謁見を他人に許すか拒むかの力を象徴するもので、このように鍵とは王国用語であった。
ひとりで学べるキリストの啓示 フルダ・K・伊藤著 文芸社
「ダビデの家」とは、エルサレムのことです。
「ダビデの家の鍵を持つ」とは、エルサレムにおける「完全な管理権を持つ」ことだと解釈できます。
ですから、イエス様が持っておられる「ダビデの鍵」とは、「完全な管理権」「御国の権威」を持っておられるということだろうと思います。私は、この解釈が正解なのだろうなと思っています。
確かに、主は「天においても地においてもすべての権威」をお持ちです。
「ダビデの鍵を持つ」とは、本当の王国の「支配者」「権威者」であるという意味だろうと思うのです。
しかし、ここで一つ、些細な事ですが疑問が生じてしまったのです。
「ダビデの鍵」と「ダビデの家の鍵」は同じなのかという疑問です。
このような疑問が湧きあがると、つくづく自分の性格が嫌になりますね(笑)
先に進めないので、無視したい気分ではありますが、一つ面白い解釈を見つけたので紹介したいと思います。
ダビデの鍵とはなんでしょうか。これは、非常にユダヤ的な言葉です。ヘブライ語でダビデの鍵というのはどういうことでしょうか。二つの意味に理解することができます。第一の意味は非常に簡単です。ダビデが仮に鍵を持っていたとすれば「ダビデが持っている鍵」ということです。第二の意味は「ダビデを理解する鍵」という意味です。文法的にはこのどちらも考えられるのですが、ユダヤ文献を見る限り「ダビデの持っている鍵」という意味での表現は一回もでてきません。しかし「ダビデを理解する鍵」という意味では何度も何度も登場します。当然、聖なる方、真実な方が持っているダビデの鍵は「ダビデを理解する鍵」と解釈すべきでしょう。
黙示録の七つの教会 ヨセフ・シュラム著 ネティブヤ日本支部
「ダビデを理解する鍵」とは、つまり「ダビデのような王であるイエス様を理解する鍵」ということです。
これは、なかなか「頭がこんがらがる」解釈ですが、不思議と心には「ストン」と落ちました。
イエス様は「ダビデの鍵」を持っておられます。そして、その鍵とは「主イエスご自身」であると言い換えることができます。もしくは「鍵とは聖霊様である」とも言えます。どちらも正解だと思います。
イエス様を通らなければ「誰も御父のもとに」行くことはできません。
イエス様は「道」であり「門」です。そして、その「門」を開く「鍵」でもあるということです。
イエス様が「鍵」を用いて「だれも閉じることのできない門」を開いてくださったのはなぜでしょう。
それはフィラデルフィアの教会が「わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかったから」だと言われます。
つまり「主のことばと主の御名を守ること」が「鍵を使って門を開いてもらうために必要だ」ということです。
私たちは自分で「門」をこじ開けることはできません。私たちは常に「開かれた門」を行くのです。
そして、ここに「門が開かれるための秘訣」が記されています。
「主のみことばと主の御名を守ること」です。それは「主イエスを理解すること」と言っても、それほど「こじつけ」ではないと思います。
「小さな群れ」ならば、そのすべての力を持って、イエス様を慕い求めましょう。「キリストの心」をうちに抱いて歩めるように、御霊の満たしを切に求めましょう。
「門を開く鍵」は、イエス様の御手にあるのです。そして、その鍵は「キリストの心」を抱く者のために用いられると私は信じます。
「少ししかない力」であっても「主のことばと主の御名」を一心に守るならば、かならず「門」は開かれるのです。
確かに、フィラデルフィアの聖徒の前に「だれも閉じることのできない門」は開かれたのです。
だれも閉じることのできない門を開いておいた
「だれも閉じることのできない門」とは何だろうと常々考えています。
ある人はそれを「宣教の門だ」と言います。
ある人は「私の進む道は閉ざされないということだ」と言います。
そして、ある人は「それは天の御国の門だ」と言います。
もちろん、それはすべて「正解」なのです。
イエス様はフィラデルフィアの教会の「前に」だれも閉じることのできない門を開かれたのです。
つまり、フィラデルフィアの教会の「歩み」は間違っていないので「そのまま進み行け」ということです。
「小さな群れ」の聖徒たちよ、恐れずに進み行けという励ましです。
「門」とは「開かれる」ものなのです。
「鍵」を持っておられるのはイエス様です。
そして、その「鍵」を用いてもらえるのは「イエス様を理解したいと願う人々」だけなのです。
主の道は「見えないところ」に造られます。主の門は「理解できないとき」に開かれます。
もしかすると、あなたの周囲の人には「開かれた門」は見えないかもしれません。あなたが、なぜ進んで行こうとしているのか理解してもらえないかもしれません。
しかし、開かれた門が見えるのならば、あなたは進んで行かなければなりません。
フィラデルフィアの教会は、すべての人に理解されたわけではありません。
「フィラデルフィア」とは「兄弟愛」という意味ですが、この教会の置かれた場所に「真の兄弟愛」はありませんでした。
ユダヤ人と自称していた人々がいました。彼らは「小さな群れ」を迫害していたと思われます。
迫害は避けられないとイエス様は言われます。
実際に彼らは「自分は神に奉仕しているのだ」と思って、聖徒たちを追いつめているのです。
救われる前のパウロがそうであったように。
現代の私たちの世界でも、主の目に映る人類は、みことばに聞き従う者たちと、キリストを退ける者たちとの二つに分かれるのです。今は、です。明日、その「サタンの会衆」の一人が、キリストの羊の囲いに入れられるかもしれません。しかし、今、この一瞬一瞬には、信じているか否かで、それぞれどちらかの陣営に身を置いているのです。
黙示録の7つの手紙 柴田敏彦著 いのちのことば社
パウロが「サタンの会衆」であったとは言いませんが、彼は確かに「的を外した熱心さ」によって「聖徒」を追いつめていました。
パウロは、自分の行いが「神を冒涜すること」だとは思っていませんでした。むしろ、神を冒涜しているのは「キリスト者」の方だと信じていました。
ゆえに迫害し、暴力をふるって、牢に投げ込んだのです。
パウロの心を変えたのは、もちろん主イエスの幻です。主がパウロに「とげのついた棒を蹴るのは痛いことだ」と言われたからです。
しかし、ステパノの殉教も影響したのではないかと思えます。
このとき、イエス様はステパノの上に「門」を開かれました。開かれた天はステパノにしか見えませんでした。
その開かれた天から流れ溢れたのは「キリストの心」です。
青年であったパウロは、このステパノの祈りを聞いたはずです。
この時、サウロ、後のパウロは、ステパノを殺すことに賛成していました。
これをきっかけに激しい迫害が起こります。青年サウロは、それは熱心に迫害に励んだのです。
しかし、主はステパノの祈りを聞き入れられました。
「この罪を彼らに負わせないでください」
私は、この祈りが聞かれたので、サウロは「パウロ」となり、主イエスのしもべへと変えられたのだと信じています。
ステパノの死をきっかけに迫害は激しくなりました。何か悪いほうへと進んで行くように見えます。
しかし、覚えてください。
天が開かれたなら、必ず「キリストの心」「神のみこころ」が注がれるのです。
聖徒の人生は、この「御国で行われているみこころ」を「地に広げていく」ことが目的なのです。
私が生かされているのは「御国の支配」を広げるためなのです。それはつまり「キリストの心」を現わすということです。
「開かれた門」が見えますか。
あなたの前に開かれた門があるのなら「キリストの心」を携えて前進せよということです。
もし、目の前の道が閉ざされているように思えて、進めないと感じているならば、そのときには「上」を見なさい。きっと「天が開けている」のを見ることができます。
そこから「キリストの心」が流れてくるのを感じることができるでしょう。
キリストの心を携えて行きます
ステパノから流れ出た「キリストの心」は、見えない領域に「御国の支配」をもたらしました。
迫害によって散らされた人々は「キリストの心」を携えて散って行ったのです。
彼らは「小さな聖徒たち」です。「少しの力しかない者たち」です。もはや「小さい群れ」でもありません。
彼らは「散らされ」ました。しかし、主は彼らの前に「門」を開かれたのです。
彼らは「福音を伝えながら巡り歩いた」のです。誰も彼らに福音を宣べ伝えることをやめさせることはできませんでした。
迫害は「キリストの心」を広げる手段とされたのです。
主は、フィラデルフィアの教会の前に「だれも閉じることのできない門」を開かれました。
彼らは「少しばかりの力」で、その門を通って行きます。そして、彼らの行く先々に「キリストの心」が流れたであろうと私は信じます。
フィラデルフィアの教会は「17世紀から19世紀の教会」を現わすと言われています。
フィラデルフィアの教会は、十七世紀から十九世紀の教会の姿を現していると言われています。この時代は、八節に「わたしは、あなたの行いを知っている。見よ。わたしは、だれも閉じることのできない門を、あなたの前に開いておいた。」とあるように、世界中に福音の「門戸が開かれ」世界宣教が盛んに行われた時期でもあります。
世の終わりが来る 奧山 実著 マルコーシュ・パブリケーション
近世海外宣教の父と呼ばれるウィリアム・ケアリーは、この時代の人です。
彼の始まりは「小さいもの」でした。妻と三人の息子(お腹の中の4人目)と、数人の仲間だけでイギリスからインドに渡りました。
しかし、彼らが海外宣教の道を開いたと言っても過言ではありません。
彼らの宣教は、苦難の連続でした。ケアリーたちが挫けなかった理由が分からないと思うほどです。
最初の妻は精神錯乱の末に亡くなりました。長男も天に召されます。
同じイギリス人からの妨害もありました。インドの人々からは「胡散臭い」と思われました。
インドの気候も身体に負担となりました。家族は赤痢にかかって苦しみました。加えて、霊的な圧迫がのしかかりました。
ケアリーは、それでも賛美をささげ宣教を続けたと言われます。そうして「キリストの心」は広がりました。彼らは自分の宣教地を心から愛しました。
彼らの残した実は素晴らしいものです。インドの奥地にまで宣教の働きは拡大しました。多くの教会が生まれました。キリスト教を土台とする学校も設立されました。聖書は、インドの40種類以上の言語に翻訳されました。
様々な妨害、苦難、悲しみが彼らの前に立ちはだかりました。しかし、宣教の御業は進んだのです。
主が「開かれた門」を閉じることは、誰にもできないことが証されました。
ケアリーが残した最も有名な言葉はこれだと思います。
「神のために大いなることを企てよ。そして、神から大きな成果を期待せよ」と。
このケアリーの言葉によって多くの人々が影響を受けました。
主が開かれた門を行く人々は、天からの力を受けるのだと私は信じます。
開かれた門を見た人は「キリストの心」を注がれるのです。
小さな群れよ。
私たちは「小さな群れ」であることを恥じることはありません。弱気になることなどないのです。
主は「小さな群れ」の前に「だれも閉じることのできない門」を開かれます。
開かれた門を行きましょう。
主が開かれた門を進むとき、私たちは「力」を受けるでしょう。それは、世の中のいう「力」ではありません。
私たちの受ける力は「キリストの心」です。
「ダビデの鍵」とは、「イエス様を理解する鍵」です。
主は「わたしのことばを守り、わたしの名を否まなかった」フィラデルフィアの教会に「門を開かれた」のです。
イエス様の「心」を理解する者にだけ「だれも閉じることのできない門」は開かれるのです。
愛する兄弟姉妹。
私たちは「主のみことばを守り、御名を否まない」者でありましょう。
どんなことがあっても「キリストを知りたい」という心を失わないでいましょう。
主を「知る」ことこそ「鍵」なのです。
そうして、主が「門を開いて」くださったなら、迷わず、進んで行きましょう。
「少しばかりの力」であってもよいのです。
「小さな群れ」であってもよいのです。
主のことばと主の御名を力を尽くして守ればよいのです。
私たちは「キリストの心」を携えて行きましょう。
祝福を祈ります。